シラバス情報
|
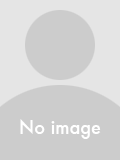
教員名 : 西嶋 亜美
|
授業科目名
美学(芸術学)特講
開講年次
1年
開講年度学期
2025年度前期、2025年度後期
単位数
4単位
科目ナンバリング
担当教員名
西嶋 亜美
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(中学校専修免許・高等学校専修免許 美術) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・教科及び教科の指導法に関する科目 この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
「芸術」に関連する様々なタイプのテキストを輪読しながら、実際の自他の芸術作品や経験と照らし合わせて議論することで、テキストを通じて世界を広げるスキルと、古今の様々な芸術実践についての知識や興味関心を獲得することが目的です。 (受講生の到達目標) 到達目標1;芸術理論や現代美術に関連する幅広い知識を得る。 到達目標2;様々なタイプのテキストを、その性質や目的に応じた仕方で読み込み理解するスキルを身につける。 到達目標3;講読テキストを出発点に議論や意見交換を行い、各々の制作や思考に生かすことができるようになる。 【授業の概要】
まず、講読の際の決まりごとの伝達をかねてテキスト(文章)を扱ううえでの引用や参照、配布資料作成の作法について確認をします(第2回〜第4回)。
その後、人を説得する文章を扱う際に基礎となる技術を、「読み・書き」合わせて実践的に学びます(第5回〜第15回)。 後期は、芸術に関わるいくつかのトピックについてテキストを講読し、話題になっている作品や社会的背景などについても議論を進めます。 この授業は、英語を扱います。また、相応の予習が必要であり、また、口頭での議論への積極的な参加が求められます。 【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第 1回:全体オリエンテーション 第 2回:テキストの扱いの基本(1):剽窃を防ぐ 第 3回:テキストの扱いの基本(2):註と参考文献 第 4回:テキストの扱いの基本(3):要約 第 5回:アカデミック・リーディング&ライティング入門(1)「アーギュメント」を見極める 第 6回:アカデミック・リーディング&ライティング入門(2)「アーギュメント」を書いてみる 第 7回:アカデミック・リーディング&ライティング入門(3)「パラグラフ」を読んでみる 第 8回:アカデミック・リーディング&ライティング入門(4)「パラグラフ」を書いてみる 第 9回:流れを意識して辞典の項目を熟読する(1) 第10回:流れを意識して辞典の項目を熟読する(2) 第11回:流れを意識して欧文を読む(1) 第12回:流れを意識して欧文を読む(2) 第13回:どこを読むべきか決める 第14回:「はじめに」で得られるもの/「はじめに」に書くべきこと 第15回:前期総括 第16回:後期オリエンテーション 第17回:オリエンタリズム批判——誰も予想していないことを論じる(1) 第18回:誰も予想していないことを論じる(2) 第19回:誰も予想していないことを論じる(3) 第20回:アートワールド——美術の歴史をとらえなおす(1) 第21回:美術の歴史をとらえなおす(2) 第22回:美術の歴史をとらえなおす(3) 第23回:フェミニズム批判——わたしの経験に意味がある(1) 第24回:わたしの経験に意味がある(2) 第25回:わたしの経験に意味がある(3) 第26回:人類学と制作論——創造行為を取り戻す(1) 第27回:創造行為を取り戻す(2) 第28回:創造行為を取り戻す(3) 第29回:創造行為を取り戻す(4) 第30回:総括 (授業の方法) 前期は講義と演習を織り交ぜ、第9回から徐々にテキストを輪読するスタイルに移行します。 テキストには英語文献を含みますので、そのつもりで参加してください。 輪読にあたっては、事前に決めた担当者がレジュメ資料を作成し、事例を挙げながら要点を発表します。ほかの参加者もテキストを読んで臨み、困難な箇所や興味深い事例に関しては、全員で議論します。 特に後期の内容については、受講生の関心を反映して変更することがあります。 テキスト・参考書
テキストは指定しません。
講読文献や参考書は随時紹介し、授業では使用するテキストは必要に応じてプリントで配布します。 参考書として、以下を挙げておきます。 阿部幸大『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』光文社、2024年 山本浩貴『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』中公新書、2019年 以下は、図書館などで参照し、自分の関心のあるトピックの見取り図を把握するのに便利です。 美学会編集『美学の事典』丸善出版、2020年 授業時間外の学修
(事前学習)
事前にテキストを読んで、疑問点に対する自らの考えをある程度明確にして臨むようにしてください。発表担当者は、さらに要点や補足事項をレジュメにまとめてきてください。 (事後学習) 新たに理解したことや、興味を持った作例について、参考図書やWebを頼りに自ら調べて深めてください。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
授業への積極的な参与:60%、講読レジュメや発表における内容理解:40% (成績評価の基準) 到達目標1;発表や議論において、芸術理論や現代美術に関連する幅広い知識を獲得し、適切に運用している。 到達目標2;テキストのタイプや講読目的に応じた仕方でレジュメ資料を作成し、要点を的確に伝え、作例や事例を紹介することができる。 到達目標3;議論に積極的に加わり、芸術的な視野を広げる意欲を見せている。 備 考
「好き・嫌い」は置いておいて、様々な作例や考え方に関心を持ち、そこから学ぶことを試みましょう。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

