シラバス情報
|
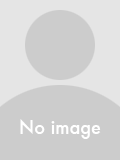
教員名 : 関下 弘樹
|
授業科目名
管理会計特論
開講年次
1年
開講年度学期
2025年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
関下 弘樹
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
原価計算論
財務会計論 次に履修が望まれる科目
特になし
【授業の目的と到達目標】
授業の目的:管理会計の考え方・意義を説明できるようになることを目的とする
受講生の到達目標: 1. 管理会計の考え方・意義を説明できる 2. 特定の問題について管理会計の視点でアプローチすることができる 【授業の概要】
企業内部を対象とした会計のことを管理会計といい、これは企業が経済活動を行う上で欠かせないものである。
本講義では、受講生がテキストの担当のテーマや論文を報告し、その内容について議論を行う。 【授業計画と授業の方法】
1. オリエンテーション
講義の全体像を説明し、報告担当を決定する 2. 管理会計は経営システムの要 管理会計の二面性について 3. 利益とは何なのか 利益計算の基本構造等について 4. 勘定合って、銭足らず 利益とキャッシュフローの違いについて 5. どの組織単位の業績を何で測るか 責任センターの設定と責任変数等について 6. 原価計算がもたらす情報と歪み 原価管理と原価計算について 7. 事業部の利益計算の難しさ プロフィットセンターの利益計算等について 8. 不用な資産増加を抑制するには 資産効率管理と測定指標について 9. アメーバ経営と時間当たり採算 アメーバ経営のメリットと難しさについて 10. 予算管理のウソ・マコト 予算管理システムの2つの顔について 11. 投資採算計算の方法と落とし穴 投資採算計算の方法について 12. 研究開発管理システムの「最適なゆるさ」とは 研究開発管理の難しさについて 13. 多様な影響システム 影響システムの重要性について 14. なぜ人は測定されると行動を変えるのか 業績測定とその落とし穴について 15. 会計を武器にする経営 現場が動き出す会計とは 全ての回で報告と議論を行う。 議論を踏まえて各回ごとの結論を得る。 テキスト・参考書
伊丹敬之・青木康晴(著). 2016. 『現場が動き出す会計』.日本経済新聞出版社.
授業時間外の学修
各回、報告資料の作成、講義内容の予習・復習を90分程度行うこと。
成績評価の方法と基準
各回の報告内容および講義内での発言(到達目標1: 40%)と最終レポート(到達目標2: 60%)で評価する。
備 考
進捗や理解度に応じて講義内容を変更する可能性がある。
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

