シラバス情報
|
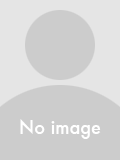
教員名 : 岩井 治樹
|
授業科目名
美術解剖学
開講年次
1年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
A-SF-112L
担当教員名
岩井 治樹
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
人のかたち (形態)、成り立ち (系統発生・個体発生)、および仕組み (機能) を学ぶことで、自身や他者の身体をイメージできるだけではなく、身体に内包されるさまざまな動物との生物学的な繋がりをイメージできるようにする。 (到達目標) 1. 人のかたちの成り立ちを進化と発生の観点からイメージすることができる。 2. 外観から人の骨および筋の位置関係を大まかに把握することができる。 3. 人のかたちを理解し、自己の作品制作に応用することができる。 【授業の概要】
洞窟壁画の記録から人は少なくとも約4万年にわたって人を描いていたことが分かっている。なぜこれほどまでに人は人に魅了され続けているのだろうか?本講義では、このような不思議な人のかたちが生まれる仕組みや規則性について、進化および発生の観点から学ぶことができる。さらに人の骨格と筋の構造を学ぶことにより、身体の外側からこれらの構造を読み取ることができるだけではなく、他の動物種とは異なる人のかたちの特殊性について理解することができる。演習では、標本を観察あるいはスケッチすることにより、動物の構造を3次元的に学ぶことができる。
【授業計画と授業の方法】
第1回 総論1 脊椎動物の歴史1 (脊索動物から両生類までの進化)
第2回 総論2 脊椎動物の歴史2 (有羊膜類から人までの進化) 第3回 総論3 人の発生 第4回 各論1 体幹の比較解剖学と発生 第5回 各論2 体幹の骨格、筋、体表解剖学 第6回 各論3 体肢の比較解剖学と発生 第7回 各論4 上肢腹側の骨格、筋、体表解剖学 第8回 各論5 上肢背側の骨格、筋、体表解剖学 第9回 各論6 下肢腹側の骨格、筋、体表解剖学 第10回 各論7 下肢背側の骨格、筋、体表解剖学 第11回 演習1 体肢の骨格と筋の3次元的な理解* 第12回 演習2 体幹の骨格と筋の3次元的な理解* 第13回 各論8 頭頚部の比較解剖学と発生 第14回 各論9 頭頚部の骨格と筋 第15回 各論10 頭頚部諸器官の形態とまとめ *第11–12回は、標本を扱うので、作業着、エプロン、マスク等持参することが望ましい。 テキスト・参考書
講義の際、資料を配布する。
授業時間外の学修
課題制作 (レポート) に向けて配布資料や参考書等をもとに準備および調査すること。
成績評価の方法と基準
成績評価の方法
・講義への参加態度 (50%)、レポート提出 (50%) による。 成績評価の基準 ・講義内容を理解し、自らの言葉や図を使って説明することができる。 ・骨や筋の位置関係を意識しながら、人を含めた動物を説明的に描くことができる。 備 考
動物の標本を扱うので、マスク、ゴム手袋、エプロン等を持参することが望ましい。動物の標本を描く場合があるので、A4程度のケント紙やデッサン道具を持参することが望ましい。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

