シラバス情報
|
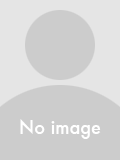
教員名 : 吉田 宰
|
授業科目名
日本文学講読4(近世)
開講年次
2年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
J-JLT-224L
担当教員名
吉田 宰
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(中学校・高等学校 国語) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・国文学(国文学史を含む。) この授業の基礎となる科目
日本文学史4(近世)
次に履修が望まれる科目
日本文学講義2(近世)
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
日本近世文学の読解に関する基本的な知識と研究方法を修得する。また主体的なテキストの読解を通して、確かな分析力および論理的思考力を身につける。 (受講生の到達目標) 到達目標1:事前にテキストの現代語訳を通読し、知らない言葉の読みや意味を調べ、正しく音読することができる。 到達目標2:講義内容を自身の言葉で正確に説明することができる。 到達目標3:講義内容を踏まえた論理的なレポートを作成することができる。 【授業の概要】
上田秋成『雨月物語』の「序文」および「夢応の鯉魚」「青頭巾」「菊花の約」を講読する。『雨月物語』は明和5年(1768)に成立し、安永5年(1776)に刊行された読本で、全9話の短編から成る怪異小説集である。本講義では諸注釈書などを活用することで、漫然と読むだけでは気づきにくい事項を確認し、作品を深く読解していく。また受講生にはテキストの現代語訳を音読してもらう。その他、中間テストおよび学期末レポートがある。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第 1回 ガイダンス:上田秋成および『雨月物語』についての概説 (講義) 第 2回 「序文」:テキストを講読する (講義) 第 3回 「夢応の鯉魚」(1):テキストを講読する (講義) 第 4回 「夢応の鯉魚」(2):同上 (講義) 第 5回 「夢応の鯉魚」(3):典拠「魚服記」を読み、「夢応の鯉魚」と比較する。論文を読み、近年の研究成果を知る (講義) 第 6回 「青頭巾」(1):テキストを講読する (講義) 第 7回 「青頭巾」(2):同上 (講義) 第 8回 「青頭巾」(3):同上 (講義) 第 9回 「青頭巾」(4):論文を読み、近年の研究成果を知る (講義) 第10回 中間テスト:第9回までの講義内容に関する筆記試験を行う (対面試験) 第11回 「菊花の約」(1):テキストを講読する (講義) 第12回 「菊花の約」(2):同上 (講義) 第13回 「菊花の約」(3):同上 (講義) 第14回 「菊花の約」(4):同上 (講義) 第15回 「菊花の約」(5):典拠「范巨卿鶏黍死生交」を読み、「菊花の約」と比較する。論文を読み、近年の研究成果を知る (講義) (授業の方法) ・第1回〜第9回、第11回〜第15回:教員が受講生に対して講義を行う。なお、受講生にはテキストの現代語訳を音読してもらう。 ・第10回:第9回までの講義内容の理解度をはかる中間テストを行う(持込不可)。 ※授業の進捗状況に応じて、適宜内容を変更する。 テキスト・参考書
(テキスト)
鵜月洋訳注『改訂 雨月物語 現代語訳付き』(角川ソフィア文庫、KADOKAWA、2006年)。その他、適宜レジュメをデータ配信する。 (参考書) 鵜月洋『雨月物語評釈』(日本古典評釈・全注釈叢書、角川書店、1969年)、長島弘明校注『雨月物語』(岩波文庫、2018年)、秋成研究会編『上田秋成研究事典』(笠間書院、2016年)。その他、適宜指示する。 授業時間外の学修
(事前学修)
テキストの現代語訳を通読し、知らない言葉の読みや意味を調べる。 (事後学修) テキストや教員が配信したレジュメの内容を復習する。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
授業中の音読10%、中間テスト(持込不可、第1回〜第9回の講義内容)50%、学期末レポート(2000文字程度の予定、第11回〜第15回の講義内容)40%。 (成績評価の基準) 到達目標1:事前にテキストの現代語訳を通読し、知らない言葉の読みや意味を調べ、授業中に正しく音読することができている。 到達目標2:中間テストにおいて、講義内容を自身の言葉で正確に説明することができている。 到達目標3:学期末レポートにおいて、講義内容を踏まえた論理的なレポートを作成することができている。 備 考
・教員の許可なく撮影、録音、スクリーンショットなどを行うことは禁止する。
・メモを取りながら受講し、また講義で取り扱わない他の短編も各自で読んでおくことが望ましい。 ・レジュメは紙媒体では配布しない。必要に応じて各自で印刷しておくこと。 ・対面/オンラインにかかわらず、授業ではTeamsの画面共有機能を使用するので、ノートPCなどの情報機器を毎回持参すること(ノートPCを強く推奨する)。 ・オンライン授業の場合:ポータルとTeamsを用いたリアルタイム授業を行う。 担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

