シラバス情報
|
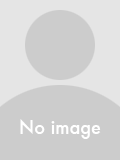
教員名 : 餅川 正雄
|
授業科目名
商業科教育法1
開講年次
3年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
C-TL-313L
担当教員名
餅川 正雄
担当形態
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための必修科目
科目区分…教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等…各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
高等学校学習指導要領(平成30年告示)に示されている商業科の目標と学習内容を理解することを目的とし、以下の項目を到達目標としています。
・1.商業科の目標と基礎的科目(ビジネス基礎・簿記・情報処理)の学習内容、指導上の留意点を説明できるようになります。 ・2.商業科の学習指導と評価の一体化の考え方を理解し、経済学・経営学などの学問領域と高等学校商業科目の関連を把握したうえで、大学での学びを教材研究に活用できるようになります。 ・3.学習指導案の基本的な構成を理解し、「簿記」の授業について学習指導案を作成したうえで、模擬授業が実施できるようになります。また、授業改善の視点を指摘できるようになります。 ・4.生徒の学力や学習葦陽等の実態を前提とした授業計画の立案を重視し、パソコン等の情報機器を活用した授業の展開を考えられるようになります。 【授業の概要】
この授業のテーマは、①商業科の基礎的科目の指導内容を学ぶこと、②簿記の授業展開ができるようになること、の二つです。①については、高等学校における商業教育は、どのような分野を対象として、具体的にどのような内容を含むかを講義を聴くことで理解することになります。商業の専門科目の中で中核的な科目の指導内容と指導上の留意点を把握していきます。そして、②については、「簿記」の目標を実現するために、そのような授業をデザインしていけばよいのかという「授業設計」を考えてもらいます。一人一人が学習指導案を作成して、「マーケティング」などの模擬授業に取り組んでもらいます。
【授業計画と授業の方法】
・第1回 高等学校学習指導要領における商業科の目標について
・第2回 商業科の4つの分野と基礎的科目について ・第3回 ビジネス基礎・簿記・情報処理の指導上の留意点 ・第4回 商業科の学習指導の特徴と指導と評価の一体化について ・第5回 商業科目の教材研究の仕方と大学での学びの関連性について ・第6回 商業科目を指導する際に、教科書や問題集をどのように活用するのか ・第7回 私の考える商業科の教育課程 商業科目の系統性・体系性とは何か? ・第8回 具体的な商業高校の教育課程から何が見えてくるか ・第9回 情報処理の授業における情報機器の活用方法 ・第10回 簿記の学習指導案の作成演習 ・第11回 模擬授業の実施と振り返り①(説明・発問に注目して) ・第12回 模擬授業の実施と振り返り②(板書・ペアワーク、グループワークに注目して) ・第13回 学習補助教材〔パワーポイント)の作成演習 ・第14回 具体的なアクティブ・ラーニングの採用方法 ・第15回 まとめ 商業教育の本質は何かを考える テキスト・参考書
・テキスト 文部科学省『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 商業編』実教出版 ¥744+税
・参考書 西村修一監修、並木秀樹編著『商業科教育法ー理論と実践』東京法令出版 ¥2,640- 授業時間外の学修
高等学校の教科書「ビジネス基礎」と「簿記」の2科目の記述内容を精読する。教科書の「索引」にある専門用語の意味を説明できるようにノートに整理しておく。
授業前の予習は、毎回2時間程度必要です。また、授業後の復習や課題についても1時間程度必要です。 成績評価の方法と基準
学習指導案 30%、「簿記」の模擬授業30%、教材研究ノート20%・課題レポート(教育課程案)20% で評価します。
備 考
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

