シラバス情報
|
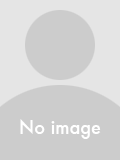
教員名 : 林 直樹
|
授業科目名
日本経済論
開講年次
2年
開講年度学期
2025年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-214L
担当教員名
林 直樹
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・商業の関係科目 この授業の基礎となる科目
経済学史、経済史
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
【目的】
(1)時代背景、思想、政策立案の相互関係を、立体的に把握する。 (2)過去と現在の日本経済を比較考量して将来の見通しを立てるための、中長期的視野を獲得する。 【到達目標】 (1)時代の中で生み出されてきた諸政策の狙いとその「意図せざる」帰結を、整理しつつ論述することができる。 (2)過去と批判的に距離を取りつつも現代に読み換えて発想する「現実的な想像力」を、駆使することができる。 【授業の概要】
テキストの著者である吉川洋氏は、高度成長は本当に「進歩」だと自信をもって言い切れるか、という表現で本文を結んでいる。これには「もちろん大進歩にきまっている」という批判の声もあったようで、吉川氏は、自分は反成長論者ではないが経済成長とはそもそも何なのかを再考せねばならないと考えているのだと、自らの真意を語り直す(中公文庫版あとがき。テキストは初め1997年に読売新聞社から刊行された)。
経済学徒は「冷静な頭脳と温かい心」を持つように諭したのはマーシャルである。その師から見てケインズの兄弟子に当たるピグーがかつて、「経済的厚生」と「非経済的厚生」はトレード・オフに陥る恐れがあることを指摘したように、経済成長概念の生みの親イギリスにおいてさえ、経済活動とその変化を適切に捕捉する物差しをめぐって、これぞ正解、という方向性が見出されているとは言いがたい状況である。そして、たとえその物差し、ないし尺度が見出されたとしてもなお、経済成長の結果として普遍的に登場しがちな「高度大衆消費社会」自体が、かつての社会以上に果たして善いものなのかどうかという問いは、消え去ることなく残り続けるのである。 この授業では、1950年代から70年代にかけての日本で生じた「高度成長」に焦点を絞り、その過程をつぶさに追いかけながら、高度成長を単に「数量」によってではなく「実感」とともに(ただし、数量を無視するわけではない)つかみ取ることを目的とする。上記の吉川氏は日本を代表するマクロ経済学者の一人であり、かつ、ちょうど高度成長期に幼稚園から大学までを駆け抜けた世代の一員である。よって、その叙述は理論的に洗練されているだけでなく、同時代人にしか語りえない具体性に溢れている。このテキストを使用すれば、半世紀以上も昔の、劇的に変化しつつある日本社会にタイムトリップしたかのような興味深い授業内容になるのではないかと、教員自身も非常に期待している。 【授業計画と授業の方法】
第 1回 今や昔:高度成長直前の日本(1)【講義&課題】
第 2回 今や昔:高度成長直前の日本(2)【講義&課題】 第 3回 テレビがきた!(1)【講義&課題】 第 4回 テレビがきた!(2)【講義&課題】 第 5回 技術革新と企業経営(1)【講義&課題】 第 6回 技術革新と企業経営(2)【講義&課題】 第 7回 民族大移動(1)【講義&課題】 第 8回 民族大移動(2)【講義&課題】 第 9回 高度成長のメカニズム(1)【講義&課題】 第10回 高度成長のメカニズム(2)【講義&課題】 第11回 右と左(1)【講義&課題】 第12回 右と左(2)【講義&課題】 第13回 成長の光と影:寿命と公害(1)【講義&課題】 第14回 成長の光と影:寿命と公害(2)【講義&課題】 第15回 おわりに:経済成長とは何だろうか【講義&課題】 テキストに沿って進める。ただし、テキストにない情報も盛り込んだ教員作成の授業レジュメを毎回用意する。教員が参考にした書籍等はその都度、授業内で知らせる。 授業においては、教員の口頭説明ならびに板書を軸に内容が展開していくため、ノートを取りやすい環境を整えて受講することが望ましい。 なお、上記の予定表に示された「課題」とはコメントシートを指す。詳しくは「授業時間外の学修」および「成績評価の方法と基準」の項を参照されたい。 テキスト・参考書
吉川洋『高度成長:日本を変えた六〇〇〇日』中公文庫(2012年)
授業時間外の学修
(事前学修)
テキストや授業レジュメの該当範囲を、あらかじめ読み込んでおくとよい。 (事後学修) 復習を兼ねたコメントシートへの取り組みにつき、毎回30分程度の自習を求める。 成績評価の方法と基準
・学期末定期試験(70%)の結果にコメントシート(30%)の提出状況を加味し、到達目標に照らして評価する。
・コメントシートには原則として毎回2点を付与し、全15回分の提出をもって30点満点とする。提出締切には余裕を持たせるため、急いて提出する必要はない。 ・試験では、定着させた知識を結合させながら自らの思考の道筋に沿った主張をなすこと、つまり論述を重んじる。授業内容を「覚える」だけでなく「理解して咀嚼する」ことが不可欠である。 備 考
・Teamsで事前に資料(レジュメ等)共有を行い、対面で授業を進めていきます。毎回、録画を行いますので、万一欠席した場合や復習に活用可能です。
・コメントシートの提出にもTeamsを使います。締切は授業当日24時とし、復習時間を充分に確保します。オンライン時代の「利器」を積極活用しながら、効率よく、同時により深くまで知識を定着させてもらえたらと願っています。 担当教員の実務経験の有無
無
実務経験の具体的内容
|

