シラバス情報
|
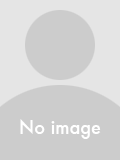
教員名 : 鳥田 友起
|
授業科目名
経済政策1
開講年次
2年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-209L
担当教員名
鳥田 友起
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・商業の関係科目 この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
経済政策2
【授業の目的と到達目標】
本講義は、経済政策に関する入門講座です。その目的は、基本的かつ多様な経済政策を理解すると共に、いかに経済政策が身近な問題と結びついているかを理解し、感じて頂く事です。加えて、経済政策の歴史にも触れることによって、該当政策が現在のどんな出来事や制度と結びついているのかを認識して頂きたいと考えています。最終的には、web上、テレビ、新聞上での経済政策に関心を持ち、それが今後の日本や国際情勢にどのような影響を及ぼすのかに関しても留意し続けて頂きたいと思っています。
到達目標1:日本における経済政策の歴史的展開を認識する。 到達目標2:経路依存論の基本について説明できる。 到達目標3:経済政策の歴史が現在の情勢にいかに影響を及ぼしているかに関する知見を深める。 【授業の概要】
本講義では、経済政策のなかでも、資本政策、産業政策、中小企業政策や労働政策といったような産業・企業に関連した経済政策に目を向ける予定です。日本型資本主義モデルは、戦前からの継続モデルなのか?戦後に形成されたものなのか?そうした日本型モデルに変遷を加えようとした「アベノミクス」とは、一体どんなものであり、どのような影響があったのか。また、日本型資本主義モデルの功罪は?1970年代の日本型資本主義の栄光を支えた中小企業の現状は?そして、日本型資本主義モデルの主要要素の1つであった雇用(従業員)をめぐる政策が、どのように変遷を遂げてきたのかをテーマとして扱います。準備学習は、必要ありませんが、理解の深化と知識の定着のために、事後学習を奨励致します。
【授業計画と授業の方法】
第1回 イントロダクション
第2回 経済政策をめぐる情勢比較 - 第3回 経済の仕組みと経済政策 - 経済、経済政策とは?? - 第4回 経済の仕組みと経済政策 - アベノミクスを見直してみよう - 第5回 日本の経済政策の歴史 - 日本型資本主義の歴史をたどる - 第6回 グローバル時代の資本主義 - 日本型経済システムは国際システムに向かった??? - 第7回 グローバル化の終焉と日本型資本主義 - SDGs時代における日本型資本主義 - 第8回 戦前の産業振興と経済政策 - 欧米列強へのキャッチアップ - 第9回 公害と産業政策 - 七色の煙は、経済復興のシンボル - 第10回 「福祉なくして経済発展はない」 第11回 中小企業の底力 - 日本経済に占める中小企業 - 第12回 中小企業政策の全体像と今後 - 中小企業の成長・生き残りこそが日本の生き残り?? - 第13回 労働政策とは? - 労働者保護と低失業率 - 第14回 規制緩和と労働政策 - ブラック、ハラスメント、貧困と格差 - 第15回 総復習 本講義では、前半に講義形式で各テーマの検討を行い、後半部分では、Active learning的にグループワークを行う予定でいます。各回のトピックに関連したテーマに基づいて、グループで協議を行ったあとで、その代表者数人が発表を行い、履修者全員でその後、議論を行うという流れを予定しています。 テキスト・参考書
【テキスト】
特に必要ありません。講義に合わせて、資料作成を行いますので、そちらを参考にして頂ければと思います。 【参考書】 入門現代日本の経済政策 (岡田知弘・岩佐和幸編:法律文化社) 授業時間外の学修
【事前学習】
テーマに応じたニュースを新聞やweb上でチェックしてください。 【事後学習】 講義資料を活用することによって、取り扱ったテーマや内容に関する見直しを行ってください。 成績評価の方法と基準
【成績評価の方法】
履修人数にもよりますが、評価基準は以下を予定しています。 15% 平常点 15% 講義中の発言 30% グループワークとグループレポート 40% 期末試験 【成績評価の基準】 各経済政策の歴史的展開、およびその影響に関する検討を毎回行います。そうした点を踏まえたうえでのグループワークとグループレポートを毎回行い、理解度の確認を行い、成績基準となります。また、講義目標に到達しているかの全体的な確認のために期末試験を行い、その理解度をチェックする予定です。 備 考
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

