シラバス情報
|
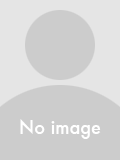
教員名 : 邵 忠
|
授業科目名
製品開発論
開講年次
2年
開講年度学期
2025年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-MN-211L
担当教員名
邵 忠
担当形態
メディア授業
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
生産管理論(生産システム論)
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
戦後日本企業内及び企業間で展開された全社的品質管理活動の実態を理解し、生産現場における 管理の7つ道具や品質管理の基礎知識などを勉強させ、品質管理の基礎の専門用語、基本的な技術と技法を習得し、活用できることを当授業の目的と到達目標とする。 (受講生の到達目標) (1)品質管理分野に関連する基礎知識や理論を説明できること。 (2)現場での品質管理の諸手法や技法を習得し、実際の課題解決に活用できること。 (3)モノづくりやサービスの現場の品質管理の問題や課題について自分の主張や考えを論じられること。 【授業の概要】
当授業科目では、工業製品及びサービスに関する品質管理の歴史、特に戦後に始まった日本的品質管理活動の展開過程を解説して、品質管理が日本経済の発展への貢献とその重要性を理解させる。主に日本企業内の全員参加の「全社的品質管理(TQC)」と「統計的 品質管理(SQC)」を内容として講義を進める。 「全社的品質管理」は、日本企業の現場発の全員参加の品質管理活動であり、欧米の専門家集団による「統計的品質管理」と一線を画す効果的な品質管理手法のQC7つ道具として、のちに世界へ広がっていった。一方、「全社的品質管理」は「統計的品質管理」を排除するものではなく、補完的に活用することによって、品質管理から品質保証へ確実に実施するのである。 この講義はオンラインで行い、プリント配信で事前予習と事後復習を奨励する。また、理解を深めるために課題を出して、受講生の日常生活における様々な品質に関する事例や体験を交えながら自身の感想や考えを述べさせる機会を与える。 【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第 1回 授業のガイダンス 第 2回 品質管理の基礎知識(1):品質の概念 品質管理は質の管理より、量の管理が重視し、管理は計画機能を持ち、管理サイクルで実施 第 3回 品質管理の基礎知識(2):品質と品質管理の定義 工程に品質を組み込む全社的品質管理とはなにか 第 4回 品質管理の基礎知識(3):品質管理の歴史 品質意識の芽生えと品質管理の誕生、戦後日本の品質管理の歴史 第 5回 品質管理の基礎知識(4):品質問題とはなにか 品質問題の対象としての品質欠陥・事故・事件、品質のコストなど 第 6回 品質管理の基礎知識(5):品質問題の対策と手段 品質意識と品質情報、PL(製造物責任)法と国際規格ISO9000など 第 7回 品質管理の基礎知識(6):統計的品質管理(SQC)の基礎 データの平均値の意義、標準偏差(σ)、確率分布など 第 8回 中間試験 第 9回 品質管理の実技(1):日本の全社的品質管理(TQC) QCストーリとQC7つ道具によるQCサークル活の展開など 第10回 品質管理の実技(2):7つ道具その一 チェックシート、パレート図 第11回 品質管理の実技(3):7つ道具その二 ヒストグラム、特性要因図 第12回 品質管理の実技(4):7つ道具その三 管理図、散布図 第13回 品質管理の実技(5):統計的品質管理の全数検査と抜き取り検査 全数検査と抜き取り検査の違い、抜き取り検査の利点 第14回 品質管理の実技(6):統計的品質管理の抜き取り検査方法 抜き取り検査方法の計算手順 第15回 これからの品質管理:全社的品質経営への発展及び諸課題 第16回 期末試験 (授業の方法) 授業は、中間試験と期末試験をを含めてすべてオンライン講義形式で行い、パワーポイントの資料を事前にTeamsに配信して、それを用いて進めていく。授業内容の理解を深めるために、事前予習と事後復習、および授業中の聴講を求める。毎回、課題を出して、次回の講義でフィードバックをする。第8回目あたりで中間試験を実施して受講生の理解度を把握し、授業の改善を図ろうとする。第16回目に期末試験を実施して、授業への理解をチェックするとともに、受講生に対する公平な成績評価を行う。 テキスト・参考書
(テキスト)
プリント配布 (参考書) 奥村士郎著「品質管理入門テキスト」日本規格協会 ※ その他、授業中に適宜に指示する 授業時間外の学修
(事前学修)
事前配布した資料を予習し、専門用語を理解すること。わからない場合、参考書やネット検索を利用して確認すること。疑問点があれば、メールや授業時に遠慮なく聞くこと。 (事後学修) 必ず期限内に課題を完成して提出すること。授業中に習った内容を復習し、理解を深めること。また、授業内容に関連する企業の品質及び品質管理の情報や事例に関心を寄せること。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
期末試験(40%)、中間試験(20%)、課題提出(40%) (成績評価の基準) 3つの到達目標に対する評価基準は下記の通りです。 (1)品質管理分野に関連する基礎知識や理論について中間試験と期末試験及び課題提出で平均6割以上正解できること。 (2)現場での品質管理の諸手法や技法、および実際の課題解決について、6割以上正解できること。 (3)モノづくりやサービスの現場の品質管理の問題や課題について自分の問題意識や主張を論じられること。 備 考
オンライン受講のため、随時に受講生からのご意見を受けさせながら、即座に授業改善に活用する。
上記の授業計画は、一応の目安であり、授業進行の状況より早めたり、遅れたりすることがある。 また、オンライン講義科目なので、誠実に授業に出席し、聴講することを求める。 担当教員の実務経験の有無
〇
実務経験の具体的内容
次の経歴・経験を持つ教員による授業
・セメントや大型陶板プラントの建設や試運転に携わった経験 ・家電のプリント基板の製造現場での品質検査の業務に携わった経験 ・自動車用板ガラス加工品の業界検査委員として、検査実施に参加した経験 ・自動車や家電及びアパレル生産ラインなど多数の現場調査の経験 |

