シラバス情報
|
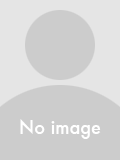
教員名 : 瀬戸 正則
|
授業科目名
経営管理論
開講年次
3年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-MN-302L
担当教員名
瀬戸 正則
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
経営学入門
経営学総論 次に履修が望まれる科目
経営組織論
日本企業論 【授業の目的と到達目標】
今日の企業社会における経営管理(マネジメント)の構造とプロセスについての知識を体系的に修得することを、本講義の目的としています。
受講生の到達目標は、以下の通りです。 (1)現実の企業社会で生起している諸問題・課題を抽出し、経営管理論から得られる知見等を用いて分析・考察し、結論が導出できること。 (2)経営管理論をはじめ、関係性のある周辺理論から得られた成果を、自らの表現で他者に説明し、理解・受容が図れること。 【授業の概要】
経営管理論は、20世紀初頭のアメリカにおける科学的管理に端を発した後、大規模化・高度化・複雑化・国際化が加速している企業活動を統括する、総合管理論として展開されています。
そして経営管理論の主たる課題は、現実的な企業活動を研究対象として、企業の経営行動において生起する多様な問題・課題を理論的・実証的に解明することにあります。 そこで、今日の企業社会における経営管理(マネジメント)の構造とプロセスについての知識を体系的に修得することを、本講義の目的としています。 【授業計画と授業の方法】
第 1回 オープニング・セッション −講義の目的・進め方・学修方法、経営管理論とは
第 2回 企業とは −企業組織の成立・特性・形態、社会的器官としての株式会社の特徴と実際 第 3回 マネジメントに関する基本的思考の変遷 −科学的管理法、人間関係論、条件適合理論 第 4回 経営管理の発展 −経営管理の系統図、経営管理の諸理論 第 5回 モティベーションと組織マネジメント −組織の活性化要件、個人と組織の意思決定、組織マネジメントの価値 第 6回 経営のリーダーシップ −リーダーの資質と役割行動、影響力とリーダーシップ論、各職位階層のリーダーシップ 第 7回 経営者の職能① −所有と経営の分離、経営者支配 第 8回 経営者の職能② −経営管理と意思決定、コーポレート・ガバナンス 第 9回 組織文化の創造と変革 −組織文化の概念定義と機能、組織文化と経営理念 第10回 企業環境 −環境適応と環境創造、企業の社会的責任、経営のグローバル化、サステナビリティ 第11回 企業戦略・競争戦略のマネジメント −経営戦略とは、経営理念と経営戦略、多角化、競争優位とは 第12回 イノベーションのマネジメント −イノベーションとは、イノベーション・メカニズム 第13回 日本の経営管理 −日本的経営の特殊性、日本企業における人のマネジメント、理念経営 第14回 経営管理論の今日的課題 第15回 フィードバック・セッション −全体の振り返り・まとめ− ※企業における経営行動の現状や課題等の実相について、教員が半構造化面接調査活動等を展開中の大企業や中堅・中小企業を中心に実例として取り上げながら、適宜解説します。 テキスト・参考書
【指定テキスト】
瀬戸正則(2017) 『戦略的経営理念論−人と組織を活かす理念の浸透プロセス』 中央経済社 ISBN:978-4-502-22611-3 【参考書】 上野恭裕・馬塲大治(2016) 『経営管理論』 中央経済社 ISBN:978-4-502-19061-2 授業時間外の学修
指定テキストは事前に読んで予習し、講義での配布資料と共に事後に復習してください。
講義内容を深いレベルで理解するためには、受講者自身で日頃から人間社会や組織現象に対する関心をもち、自学自習の継続的な努力が求められます。 とくに、日常生活上の身近な存在でもある企業に対し日頃から積極的に関心をもち、企業経営に関連した文献・新聞記事等に目配りして下さい。 講義毎に30分以上は予習・復習して下さい。とくに復習では、講義メモの再確認・加筆修正等に心掛けて下さい。 成績評価の方法と基準
〇定期試験(授業全体の理解度確認):70%
〇小テスト(2回程度実施し、授業の前半と後半における理解度について確認):25% 〇授業参加度評価(質疑応答等での積極的な履修姿勢等):5% 上記の方法と基準に基づき、総合的に評価します。小テストについては、毎回実施後に採点結果を概説し、学習上のポイント等をフィードバックします。 備 考
授業計画については、受講生の理解度や講義の進捗等を考慮し、一部変更する場合があります。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

