シラバス情報
|
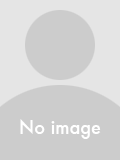
教員名 : 森本 幾子
|
授業科目名
地域経済史
開講年次
3年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-303L
担当教員名
森本 幾子
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
経済史,日本経済史
次に履修が望まれる科目
日本経済論
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
本講義ではおもに,19世紀に発行された「仕切状(しきりじょう)」と呼ばれる商取引文書や商業チラシであった「引き札」を解読することによって,尾道を中心とした瀬戸内地域と日本海地域の北前船商人との商取引の特徴を学ぶ。明治期に鉄道が全国に敷設されるまで,日本では,北前船をはじめとする諸国廻船の活動が活発化し,明治20年代頃まで地域間価格差によって利潤を得ていた。これらの廻船は,その資本をもとに各地に近代的な企業を設立し,地域経済の近代化をけん引した。この講義では,おもに「仕切状」と「引き札」の解読によって,当該期の商品流通の実態や商業情報が商取引に与えた影響などを理解し,廻船活動による資本蓄積が地域経済および日本経済の近代化に果たした役割について理解することを目的とする。 (到達目標) 到達目標1:19世紀における商品流通と日本経済の関係を理解すること。 到達目標2:「仕切状」「引き札」の解読ができるようになること。 到達目標3:商業情報の発信が商取引に与える影響を理解すること。 【授業の概要】
1990年代以降,商品流通史研究の分野では,とくに幕末〜明治期の廻船経営に関する分析が進み,当時の商品流通と日本経済の関係が実証的に明らかにされつつある。このような研究状況をふまえ,本講義ではおもに,19世紀における商品流通のと地域経済の特徴を,北前船など諸国廻船の活動を通して考える。とりわけ講義では,「仕切状」や「引き札」の解読を通して,商取引方法や商業情報の発信について学び,現在とも比較しながら,当時の商品流通と地域経済および日本経済発展の関係について理解を深める。
【授業計画と授業の方法】
第1回 ガイダンスー19世紀における瀬戸内地域の景観と経済活動の特徴−
第2回 19世紀における日本の商品流通と地域経済の発展 第3回 仕切状から読み解く−読み方を学ぶ① 第4回 仕切状から読み解く−読み方を学ぶ② 第5回 仕切状から読み解く−取引商品の特徴① 第6回 仕切状から読み解く−取引商品の特徴② 第7回 仕切状から読み解く−商品の地域間価格差 第8回 仕切状から読み解く−「尾道ブランド」の創出 第9回 商業情報の発信①−読み方を学ぶ 第10回 商業情報の発信②−「引き札」(商業用チラシ)の効用Ⅰ− 第11回 商業情報の発信③−「引き札」(商業用チラシ)の効用Ⅱ− 第12回 商業情報の発信④−『備後の魁(さきがけ)』にみる明治期の店舗情報 第13回 商業情報の発信⑤−大正期の「絵葉書」にみる尾道港の発展ー 第14回 流通の担い手の変化と地域経済−廻船から鉄道へ− 第15回 まとめ (授業の方法) 講義は、15回すべて資料を用いる。資料は講義の前に,teamsおよびポータルサイトにアップロードするので,必要があれば,講義が開始される前までに各自印刷をしておくこと。 講義では必要事項を板書するので,配布プリントに各自記入すること。板書を写真撮影することは禁止している。講義回によっては課題を出題し,それに対する回答を求めることがある。回答のフィードバックは,次回講義時のはじめに行う。 テキスト・参考書
必要に応じて講義プリントを配る。
授業時間外の学修
成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
前期認定試験(100%)ただし、講義中の課題コメントシートを6割以上提出していること。 (成績評価の基準) 到達目標1:19世紀における商品流通と地域経済の特徴について述べることができるようになること。 到達目標2:「仕切状」「引き札」の解読ができるようになること。 到達目標3:19世紀の商業情報発信が商取引に与えた影響について述べることができるようになること。 備 考
1.「仕切状」「引き札」とも江戸〜明治中期の文字(古文書(こもんじょ))で書かれているため,これらの文字を読む意欲のある方の受講が望ましい。
2.毎回配布資料とパワーポイントを使用し,全回「講義」形式で進める。 3.講義プリントをよく読み,予習・復習(各回予習・復習とも30分程度)を行うこと。 4.板書や画面内容の写真撮影は禁止している。必ず自筆すること。 担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

