シラバス情報
|
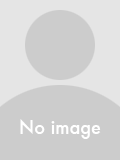
教員名 : 林 直樹
|
授業科目名
基礎演習1
開講年次
1年
開講年度学期
2025年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-CS-101S
担当教員名
林 直樹
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
【目的】
(1)テキストを素材として、問題を発見することを習慣づける。 (2)プレゼンテーションやディスカッションに必要な基本スキルを修得する。 【到達目標】 (1)テキストの論旨を精確に読解し、的確なレジュメを作成することができる。 (2)レジュメをふまえながら自らの意見を練り上げ、明確に発表することができる。 【授業の概要】
東浩紀氏はテキストの結びで、「ぼくは論壇では評判がよくありません」と書いている。そうかもしれないが、『動物化するポストモダン:オタクから見た日本社会』(2001年)以来、広い意味での論壇の一角にはつねに東氏の姿があった。嫌われるとしたら、左にも右にも率直な言葉を浴びせるその自由なもの言いに理由はありそうだ。しかし、日本を含めた昨今の社会に欠けているのは、まさにそういう「とらわれない姿勢」なのではないだろうか。
SNSの政治利用を筆頭に、「ノンポリ(=政治とは無縁の立場)」が許されないかのようなギスギスした空気が広がる現代で、あえて「自分が間違っていた」と切り出す話し手の勇気、そして「よくぞ言った、ではどの立場が正当か一緒に考えよう」と応じる聴き手の度量。誰もが隙を作りたがらない中、公の場で稀にしか見られなくなってしまったそれら双方向的な余裕を、「訂正する力」の発揮と命名した東氏。東氏自身は18世紀フランスの思想家ルソーの作風に学んだようだが、哲学・思想の書としても、社会学の書としても、(あえて経済学に引きつけて言えば)「ナッジ」に着目した書としても、このテキストを読むことができる。 この授業では、流行りの文系不要論や人工知能・シンギュラリティ論すら単に流行の受け売りの範疇に留めない、多岐にわたって非常に冴えた東氏の現代社会批評の数々に、じっくり耳をすませてみたいと思っている。入学したての受講者の皆さんにとって、退屈することのない思考の整理につながることだろう。 【授業計画と授業の方法】
第 1回 はじめに【講義&演習】
第 2回 なぜ「訂正する力」は必要か(1)【演習&課題】 第 3回 なぜ「訂正する力」は必要か(2)【演習&課題】 第 4回 なぜ「訂正する力」は必要か(3)【演習&課題】 第 5回 なぜ「訂正する力」は必要か(4)【演習&課題】 第 6回 「じつは……だった」のダイナミズム(1)【演習&課題】 第 7回 「じつは……だった」のダイナミズム(2)【演習&課題】 第 8回 「じつは……だった」のダイナミズム(3)【演習&課題】 第 9回 「じつは……だった」のダイナミズム(4)【演習&課題】 第10回 親密な公共圏をつくる(1)【演習&課題】 第11回 親密な公共圏をつくる(2)【演習&課題】 第12回 「喧騒のある国」を取り戻す(1)【演習&課題】 第13回 「喧騒のある国」を取り戻す(2)【演習&課題】 第14回 「喧騒のある国」を取り戻す(3)【演習&課題】 第15回 おわりに【講義&演習】 個人発表とグループ発表の二本立てで構成される。「課題」とあるのは発表に向けた準備を指す。 まず初めに受講者全員が一人ずつ、テキストの分担範囲の要約紹介を中心とした個人発表(レジュメを作成)を行っていく。 それらがすべて済んだ段階でグループを組み、テキストの残余範囲を軸とした総括的な発表(パワーポイント資料を作成)を行う。 教員はテキストの内容に適宜解説を加え、受講者同士のディスカッションを促しながら、個人・グループ発表内容の掘り下げを手助けする。 テキスト・参考書
東浩紀『訂正する力』朝日新書(2023年)
授業時間外の学修
(事前学修)
発表準備を怠らないこと。自らの担当範囲以外についても、テキストを読んでおくこと。 (事後学修) 発表後に得たフィードバックを記憶に留めておくこと。そして次回以降の発表に活かすこと。 成績評価の方法と基準
個人発表とグループ発表における水準を、到達目標に照らして評価する。両者のウェイトは50%ずつである。
備 考
個人発表とグループ発表の場では、単なる「レポート」に終始しないよう、論点や疑問点を含めた「皆さん自身の意見」を積極的に提示するよう心がけてください。
担当教員の実務経験の有無
無
実務経験の具体的内容
|

