シラバス情報
|
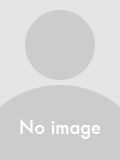
教員名 : 灰谷 謙二
|
授業科目名
研究指導(論文指導)Ⅱ
開講年次
学年指定なし
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
灰谷 謙二
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
研究指導(論文指導)Ⅰ
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
一次資料・実地調査データによる論構築と関係資料の精査をもとに、自らの見解を明確に構築・提示する。学問領域内での自分の研究の位置づけを意識し、独創性と堅実性のある実証的な論文執筆をおこなう。 1・2に順序はないが、1をふまえた執筆プロセスとする。 (受講生の到達目標)(知識・技能) (知識・技能) 到達目標1:日本語学に関する深い学識と高度な研究方法を修得し、周辺領域の考え方や理論と関連付けながらそれらを活用することができる。 (思考力・判断力・表現力) 到達目標2:実地調査と関係資料の精査をもとに、論理的に思考し、設定した課題の探究に取り組むことができる。 (主体性) 到達目標3:豊かな人間性と幅広い視野をもち、高度な言語運用能力を発揮して他者と議論や対話を行い、探究の成果を社会に発信することができる。 【授業の概要】
修士レベルの課題の大きさと広がり、方法の徹底、先行論の丁寧な検証を通して、堅実な修士論文執筆を実現するための研究指導をおこなう。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
執筆期 第1回 執筆内容の再検討 第2回 執筆開始 データをハンドリングと傾向・仮説的見通しの言語化。 第3回 目的に合わせたデータの加工。 第4回 グラフ・表の活用 適切な質・量のデータを効率的に可視化。 第5回 論構成の設計 第6回 草稿の検討 第7回 第三者からの意見をもらう(学会発表・添削) 第8回 進度に応じた計画の修正 データ収集宇調査進行状況、分析結果の状況に応じて研究計画を修正する。 第9回 問題の拡散と収束 問題意識の広がりを意識しながら、修士論文としての決着を考えて収束させる 第10回 活かすために捨てる 最終的に述べたい論の本質を活かすために、周辺的なデータを捨てる。 第11回 論をつめる ディテールを整える。用語・方法の穴をつぶしていく。注をととのえる。 第12回 構成の確認・文献リストの確認 全体の章立てのアンバランスをチェックする。文献リストの漏れ間違いをチェックする。 第13回 校正作業・印刷・しあげ・製本・提出 第14回 口頭試問準備 第15回 総括・今後の展開の整理 (授業の方法) 論文執筆の進行イメージにあわせた学修・作業の内容を論文指導のシラバスのかたちで示したもので、指導内容と指導順序・時期の進行は学修者の状況によって柔軟に変更対応する。 テキスト・参考書
とくに指定はしない。設定研究課題に応じて適宜提示する。
授業時間外の学修
(事前学修)入学時にたてた研究計画とスケジュールにそって、各自の作業をすすめ、授業前日にその週の作業をファイルで報告します。授業はその報告にもとづいて個別の指導や全体指導につなげます。
(事後学修) 指導や討議の内容を踏まえて、内容を修正し、次回作業の準備をします。 成績評価の方法と基準
(評価の方法)
研究課題の立案から資料収集の方法と実施、先行論の吟味、論構成、調査方法の吟味と修正実施をふくめた論文の完成度を副査との口頭試問と合わせて総合的に評価します。 (評価の基準) (知識・技能) 到達目標1:修士論文作成に必要な学識と高度な研究方法を修得し、周辺領域の考え方や理論と関連付けながらそれらを活用することができている。 (思考力・判断力・表現力) 到達目標2:実地調査と関係資料の精査が実施でき、資料を基にした研究課題の遂行に取り組むことができている。 (主体性) 到達目標3:豊かな人間性と幅広い視野をもち、高度な言語運用能力を発揮して他者と議論や対話を行い、探究の成果を社会に発信することができている。(日本文学論叢や文学三昧での発表機会を活かしている) 備 考
授業展開、資料配布、等にはポータルとTeamsを活用し、オンライン化した場合は、基本オンタイムの会議機能によるディスカッション形式の指導とする。あわせて個々の状況にあわせて文字ベースでのチャット・メールを活用した指導を補助的に展開する。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

