シラバス情報
|
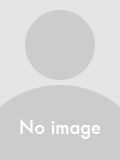
教員名 : 灰谷 謙二
|
授業科目名
日本文学・言語文化総論
開講年次
1年
開講年度学期
2024年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
灰谷 謙二
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
日本の文学と言語文化を総合的に捉える視点と方法を学びます。基幹科目を中心に専門領域の知見や方法論を横断的に学び、自分の研究・制作と有機的に関連付けられるようになることをめざします。 (受講生の到達目標) 到達目標1;日本文学・日本語学・漢文学の基幹科目、専門科目領域に関する高度な研究内容と研究方法を理解する。(知識技能) 到達目標2;日本文学・言語文化についての総合的な視点から、自分の専門領域との関連性・展開を考えることができ、それを論理的に表現することができる。(思考力・判断力)(主体性) 【授業の概要】
日本語学・近現代文学・古典文学・漢文学・米文学・地域文学の各分野について、先端的で高度な研究内容・研究方法問について、分野横断のうえ相互の関連付けを考えながら学びます。オムニバス形式で7人の担当者が2回ずつ担当し講義形式で進めます。専門性を深めながらも、閉鎖的にならない、学際的な視点と方法とはどのようなものか、自身の研究との関係を確認しながら理解していきます。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 講義 ガイダンス(灰谷) 第2回 講義 日本古典文学①日本古典文学①日本中世文学の内、和歌・連歌などの韻文を取り上げ、中世文学の特質について考察する。(藤川) 第3回 講義 日本古典文学②日本古典文学②日本中世文学の内、物語や随筆などの散文を取り上げ、中世文学の特質について考察する。(藤川) 第4回 講義 日本語学①方言研究における調査の理念と方法(灰谷) 第5回 講義 日本語学②方言研究における資料の扱い方(灰谷) 第6回 講義 日本近代文学①近現代文学の中から著名な短編小説を取り上げ、テクスト論的視点から分析・読解をおこなう。(柴) 第7回 講義 日本近代文学②近現代文学の中から著名な短編小説を取り上げ、テクスト論的視点から分析・読解をおこなう。(柴) 第8回 講義 漢文学⓵中国文学史の視点から中国の六朝志怪小説をとりあげ、日本の古典文学にうかがえる中国文学の受容について比較考察し、日中両国の文化・文学の相似性・相違性について考える。(鷹橋) 第9回 講義 漢文学②中国文学史の視点から中国の唐代伝奇小説をとりあげ、 日本の古典文学にうかがえる中国文学の受容について比較考察し、 日中両国の文化・文学の相似性・相違性について考える。(鷹橋) 第10回 講義 米文学① 現代日本文学・文化を考える上で無視出来ない欧米主導によるグローバル化の中で、間テキスト的に展開する言語文化の位置をアメリカの事例を中心に検証する。その際、従来の文字テクストの枠組みにとらわれることなく、現代のメディア事象を広く考察の対象とする。 (小畑) 第11回 講義 米文学②現代日本文学・文化を考える上で無視出来ない欧米主導によるグローバル化の中で、間テキスト的に展開する言語文化の位置をアメリカの事例を中心に検証する。その際、従来の文字テクストの枠組みにとらわれることなく、現代のメディア事象を広く考察の対象とする。 (小畑) 第12回 講義・討議 地域文学①身近な事例を文献学的方法と民俗学的方法により分析する。(藤井) 第13回 講義・討議 地域文学②身近な事例を仏教学的方法と神道学的方法により分析する。(藤井) 第14回 講義 言語・文学・表現①(新任) 第15回 講義 言語・文学・表現②(新任) (授業の方法) 基幹科目、専門科目等の担当者が1分野2回ずつを基本として、オムニバスで展開しまます。それぞれの分野の専門的な研究成果や方法について講義・討議形式をとりながら実施します。 テキスト・参考書
各回担当者から適宜指示する
授業時間外の学修
(授業時間前の学修)
シラバスに示された内容について用語検索等の準備をしておく。 (授業時間後の学修) 講義後の課題指示等に対応する。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
各回の小テスト・レポートの(50パーセント)課題・レポート等への対応(30%)、授業への取り組み(20%)についての評価を、担当者評価を総合しておこなう。 (成績評価の基準) 到達目標1;日本文学・日本語学・漢文学の基幹科目、専門科目領域に関する高度な研究内容と研究方法について理解できている。(知識技能) 到達目標2;日本文学・言語文化についての総合的な視点から、自分の専門領域との関連性・展開を考えることができ、それを論理的に表現することができている。(思考力・判断力)(主体性) 備 考
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

