シラバス情報
|
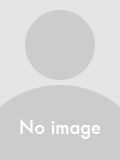
教員名 : 森本 幾子
|
授業科目名
日本経済史特論
開講年次
1年
開講年度学期
2024年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
森本 幾子
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(講義の目的)
本講義の目的は、学部での修学を基礎として、より専門的な経済史に関する知識を学ぶことです。近年の日本経済史の研究動向や研究の流れについて書かれた文献を読むことによって、大学院の調査研究の場に必要な学修に応用できる力を身に着けます。 (受講生の到達目標) 到達目標1:近年の日本経済史研究の動向に関する知識について説明できるようになること。 到達目標2:テキストを輪読することによって、著者の見解を習得し、さらに自分の意見が述べられるようになること。 到達目標3:発表をもとに、テーマに対する一定字数の論考ができるようになること。 【授業の概要】
本講義では、一冊の共通書籍を輪読することによって、現在の身近な経済活動から日本経済史の方法論について学びます。例えば、地球環境問題、エネルギー問題、災害、人口減少、医療体制の確保、教育と労働、社会福祉など、これらは日本経済の歴史や構造と密接に結び付いています。このような具体的な事例を通して、日本経済の特徴と課題について考察し、各自意見交換を行います。
【授業計画と授業の方法】
第1回 ガイダンスー講義の進め方ー
第2回 現在の世界経済と日本 第3回 家族・地域社会と経済活動 家族と経済活動、「村」の役割 第4回 災害と飢饉 経済社会化と飢饉、災害・飢饉への対応 第5回 森林資源と土地所有 森林資源利用の歴史、近現代日本の森林資源と過少利用問題 第6回 エネルギーと経済成長 石炭とイギリス産業革命、エネルギー革命と「東アジアの奇跡」 第7回 人口で測る経済力 現代社会の人口と経済、人口に関する理論、経済成長と人口 第8回 健康と医薬 生計と家計に見る健康と医薬、現代の健康と医薬、感染症流行と経済発展 第9回 これまでのまとめ 第10回 娯楽と消費 娯楽の産業化と消費社会、大衆消費社会論 第11回 教育と労働 産業社会・労働の誕生と教育、子どもと女性からみた「教育」と「労働」 第12回 法と福祉 慈善事業の時代、社会福祉の時代 第13回 帝国と植民地経済 戦争と日本帝国の拡張、日本貿易の特徴 第14回 著書に関する意見交換① 第15回 著書に関する意見交換② (講義の方法) 本講義では、日本経済史に関する著書を輪読します。それぞれ担当箇所を決め、その部分について内容をまとめ、自分の意見を発表します。毎回受講者全員で意見交換を行うことによって内容に対する理解を深めます。最後に、著書の内容に沿ったレポートを提出してもらいます。 テキスト・参考書
中西聡編『経済社会の歴史』(名古屋大学出版会、2017年)
*各自購入すること。 授業時間外の学修
事前学修:輪読の担当箇所について、十分な時間をかけて内容を理解しつつまとめること。
事後学修:自分や他の受講生の発表後、講義内で議論したことを次回の発表に活かせるよう復習しておくこと。 成績評価の方法と基準
講義への参加および発表(70%)
レポート課題(30%) (成績評価基準) 到達目標1:近年の日本経済史研究の動向に関する知識について説明できているかどうか。 到達目標2:テキストを輪読することによって、著者の見解を習得し、さらに自分の意見が述べられたかどうか。 到達目標3:発表をもとに、テーマに対する一定字数の論考が執筆できているかどうか。 備 考
①無断欠席は認めない。
②予習・復習はしっかりと行うこと。 ③授業の内容は、前後することがある。 担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

