シラバス情報
|
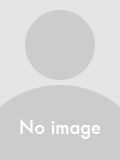
教員名 : 有吉 勇介
|
授業科目名
情報基礎理論
開講年次
2年
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-IN-208L
担当教員名
本田 治、有吉 勇介
担当形態
オムニバス
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
情報とコンピュータ
プログラミングⅠ 次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
情報科学・情報技術の基本的事項を説明できるようになる。また、情報科学・情報技術の基礎的な計算ができるようになる。 (受講生の到達目標) ハードウェア、オペレーティングシステム、情報セキュリティ管理、プログラムの4分野について 1: 基本的事項を説明できるようになる 2: 基礎的な計算ができるようになる 【授業の概要】
この科目は「情報とコンピュータ」等で学んだ情報科学・情報技術の知識をより深めるための科目です。これらの知識は、情報技術者はもちろん、情報を使いこなすことを求められる現代の社会人にとって必要不可欠なものです。この科目では、CPU・メモリ等のコンピュータハードウェアの基本的な仕組み、オペレーティングシステムの基礎、情報セキュリティ管理の基本、データ構造とアルゴリズムなどプログラムの基礎理論等について学習します。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第 1回 ハードウェア基礎1 コンピュータの構成要素、CPUの仕組み(講義) 第 2回 ハードウェア基礎2 メインメモリの管理、キャッシュメモリの管理(講義) 第 3回 ハードウェア基礎3 入出力装置の仕組み、補助記憶装置の仕組み(講義) 第 4回 基本ソフトウェア1 OSの概要、プロセスの3状態 (講義) 第 5回 基本ソフトウェア2 プロセス・スケジューリング方式、排他制御(講義) 第 6回 基本ソフトウェア3 実記憶管理、仮想記憶管理(講義) 第 7回 (前半)ハードウェア基礎の復習と確認 (後半)基本ソフトウェア4 入出力制御(講義) 第 8回 情報セキュリティ管理1 情報セキュリティ管理の基本(講義) 第 9回 情報セキュリティ管理2 ISMS(講義) 第10回 (前半)基本ソフトウェアの復習と確認 (後半)情報セキュリティ管理3 リスク管理とインシデント対応(講義) 第11回 プログラム基礎1 配列、リスト、キュー、スタック(講義) 第12回 プログラム基礎2 木構造と二分探索(講義) 第13回 プログラム基礎3 AVL木による二分探索(講義) 第14回 プログラム基礎4 バブルソート、クイックソート、チェイン法(講義) 第15回 プログラム基礎5 マージソートとヒープソート(講義) (授業の方法) 講義資料は、ポータル・Teams等で配るので、事前学習に役立てて下さい テキスト・参考書
ポータル・Teams等に講義資料をアップロードするので、各自でダウンロードして下さい。
授業時間外の学修
(事前学修)
講義資料を確認し、学習内容を把握しておいて下さい。 (事後学修) 課題等がある場合は、期限までに完成させて指定の場所に提出して下さい。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
毎授業の課題提出等:約33%程度 期末試験:約67%程度 (成績評価の基準) ハードウェア、オペレーティングシステム、情報セキュリティ管理、プログラムの4分野について 1: 基本的事項を説明できる 2: 基礎的な計算ができる 備 考
本田(ハードウェア基礎、プログラム基礎)と、有吉(オペレーティングシステム,情報セキュリティ管理)とによるオムニバス授業の予定です。
担当教員の実務経験の有無
〇
実務経験の具体的内容
企業でのシステム設計等に関わったことのある教員による授業
|

