シラバス情報
|
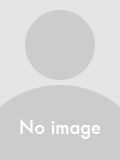
教員名 : 有吉 勇介
|
授業科目名
プログラミング1
開講年次
1年
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-IN-104L
担当教員名
有吉 勇介
担当形態
メディア授業
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 情報) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・コンピュータ・情報処理(実習を含む。) この授業の基礎となる科目
情報活用基礎Ⅰ
次に履修が望まれる科目
プログラミング2
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
簡単なプログラムを読んで理解し、説明できるようになる。プログラミングの基本事項を理解し、簡単な説明ができるようになる。 (受講生の到達目標) 到達目標1: 入出力や基本的な制御構造(順次、分岐、繰り返し)などのプログラムの流れを説明できるようになる。 到達目標2: 変数や型、配列などの基本的なデータ構造を説明できるようになる。 到達目標3: メソッドなどによるプログラムの部品化について説明できるようになる。 到達目標4: 簡単なプログラムを作成できるようになる。 【授業の概要】
現在、ほとんどのソフトウェアはCやJavaなどの手続き型という種類のプログラミング言語で作成されています。この授業では、手続き型言語によるプログラム作成のための基本事項や文法等について学びます。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第 1回 プログラミング入門(講義、演習) 第 2回 変数と型(講義、演習) 第 3回 式と代入、計算と演算子(講義、演習) 第 4回 条件と分岐1:if文の基本(講義、演習) 第 5回 条件と分岐2:複雑な選択(講義、演習) 第 6回 繰り返し1:while文(講義、演習) 第 7回 繰り返し2:fоr文(講義、演習) 第 8回 フローチャート(講義、演習) 第 9回 配列(講義、演習) 第10回 プログラムの部品化、メソッド1:呼出しと引数(講義、演習) 第11回 プログラムの部品化、メソッド2:戻り値(講義、演習) 第12回 ファイル入出力(講義、演習) 第13回 データ構造とアルゴリズムの基礎1:ソート(講義、演習) 第14回 データ構造とアルゴリズムの基礎2:探索(講義、演習) 第15回 応用とまとめ(講義、演習) (授業の方法) 授業は15回全て、講義動画の視聴によるオンデマンド方式で行う。各自で講義動画を視聴し、毎回の課題を行ない提出します。講義資料は事前にTeams等で配るので、テキストと合わせて事前学習に役立てて下さい。 テキスト・参考書
資料(スライド)を配布します。
(参考書) 『新・明解 Java入門 第2版』 柴田 望洋, SBクリエイティブ 授業時間外の学修
(事前学修)
授業資料を確認し、学習内容を把握しておいて下さい。 (事後学修) 授業で取り上げた練習課題を完成させ、期限までに指定の場所に提出して下さい。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
平常点:毎授業の提出課題:約40%程度 期末試験:約60%程度 (成績評価の基準) 目標1: 授業で提示した、入出力や基本的な制御構造(順次、分岐、繰り返し)などのプログラムの流れを説明できる。 目標2: 授業で提示した、変数や型、配列などの基本的なデータ構造を説明できる。 目標3: 授業で提示した、メソッドなどによるプログラムの部品化について説明できる。 目標4: 授業で行った練習問題のプログラムを自力で作成できる。 備 考
原則、プログラミングⅠ実習と同時受講して下さい。
プログラミングⅠ実習でしっかり復習して下さい。 担当教員の実務経験の有無
〇
実務経験の具体的内容
企業でのシステム設計等に関わったことのある教員による授業
|

