シラバス情報
|
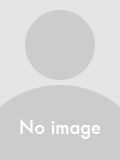
教員名 : 前田 謙二
|
授業科目名
専門演習1a
開講年次
3年
開講年度学期
2024年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-CS-301S
担当教員名
前田 謙二
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
簿記入門、租税論、税務会計論
次に履修が望まれる科目
専門演習1b
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
専門演習1aの目的は、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法などの基本的な仕組みを条文を読むことも含めて理解することです。また、判決の原文を読むことで、法的三段論法による文章構成も理解でき、判例評釈で法解釈の意味を理解することです。これらを通じて、法的なものの見方の基礎を修得し、適切な議論ができることを目指します。 (受講生の到達目標) 到達目標1:所得税法、法人税法、消費税法、相続税法などの基本的な仕組みを説明できる。 到達目標2:法的三段論法により判決の原文からポイントを読み取れる。 到達目標3:判例評釈を作成や発表し、適切な議論ができる。 【授業の概要】
前半は租税法(所得税法、法人税法、消費税法、相続税法など)の基本的な仕組みを条文の読み方も含めての講義していきます。その後、判決の読み方(法的三段論法を含む)を講義した後に、グループに分かれて選んだ判決の判例評釈をレポート作成し、プレゼンテーションしてもらい、みんなで議論します。なお、法律知識が全く無い学生を想定して、租税法を一から勉強していきます。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 オリエンテーション 第2回 租税法の基礎概念(講義・議論) 第3回 所得税法(講義・議論) 第4回 所得税法(演習) 年末調整の練習問題 第5回 所得製法(演習) 確定申告の練習問題 第6回 法人税法(講義・議論) 第7回 法人税法(演習) 別表四・五の作成問題 第8回 消費税法(講義・議論) 第9回 相続税法(講義・議論) 第10回 判決の読み方(講義・議論) 第11回 判例評釈の作成方法(講義・議論) 第12回 判例評釈(演習) グループ1の発表 第13回 判例評釈(演習) グループ2の発表 第14回 判例評釈(演習) グループ3の発表 第15回 判例評釈(演習) グループ4の発表 (授業の方法) 租税法や所得税法の基礎を講義したの後、身近な給与所得に関する年末調整や確定申告書の作成を国税庁のHPのソフトを利用し、実際に作成していきます。前半は必要最低限な租税法の知識を講義しますが。講義での問いの投げかけなどから、学生の興味のある分野で具体的な問題も提示し議論していきます。後半は、グループ分けして、判例百選から代表的な判例を選び判例評釈を発表してもらい、その判決に必要な税法知識を解説し、議論します。皆さんの議論への積極的な参加を歓迎します。 テキスト・参考書
(テキスト)
必要なレジメは事前に配付します(teams)。 中里実ほか『租税判例六法(6版)』(有斐閣、2023)、中里実ほか『租税判例百選(7版)』(有斐閣、2021) (参考書) 谷口勢津夫ほか『基礎から学べる租税法(3版)』(弘文堂、2022)や辞書代わりに金子宏『租税法(24版)』(弘文堂、2021)、より深い理解には、佐藤英明『スタンダード所得税法(4版)』(弘文堂、2024)、渡辺徹也『スタンダード法人税法(3版)』(弘文堂、2023)、佐藤英明=西山由美『スタンダード消費税法』(弘文堂、2022)など。 授業時間外の学修
(事前学修)
講義に関しては、事前に配付されるレジメに目を通す、参考書などの該当部分を読んでおく。判例評釈のグループ発表に関して、判例の原文を図書館のデータベースから入手し、グループで議論して判例評釈を作成し、発表の準備をして下さい。 (事後学修) 前半の租税法の基礎知識の修得に関しては、授業での質問等で興味を持った部分は参考書等で自分でも調べてみてください。また、発表した判例評釈での議論で回答できなかったものは、グループで回答を作成し次回報告してください。また、発表されたレポートなどに赤ペンを入れますので、どこが改善の余地があるのかを復習して下さい。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
判例評釈とプレゼンテーション(60%) 授業中の発言や質問など、授業への参加態度(40%) (成績評価の基準) 到達目標1:所得税法、法人税法、消費税法、相続税法などの基本的な仕組みを説明できる。。 到達目標2:法的三段論法により判決の原文からポイントを読み取れる。 到達目標3:判例評釈を作成や発表し、適切な議論ができる。 備 考
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

