シラバス情報
|
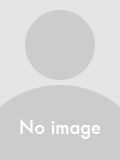
教員名 : 森本 幾子
|
授業科目名
日本経済史
開講年次
2年
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-EC-213L
担当教員名
森本 幾子
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
経済史
日本経済論 次に履修が望まれる科目
地域経済史
日本経済論 【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
現在の日本は、少子高齢化社会となり、今後も人口減少が進むと推定されている。本講義では「歴史人口学」の方法論を理解し、人口増加、停滞、減少の原因を歴史的に読み解くことによって、現在の少子高齢化社会についてあらためて問い直すことを目的とする。 (受講生の到達目標) 到達目標1:縄文時代から現代までの日本の人口動態の歴史的変遷を理解できていること。 到達目標2:江戸時代の人口増加、停滞、減少の要因について理解できていること。 到達目標3:現在の少子高齢化が歴史的なシステムの転換点であることを理解できていること。 【授業の概要】
本講義では、とくに「歴史人口学」研究の成果が最も多い日本近世(江戸時代)の人口動態の特徴を、自然、社会、経済、技術、市場経済化などの諸要素や人々のライフサイクルとの関係から紹介する。また、現在の少子高齢化社会と比較することによって、今後の人口問題について考える機会を提供する。
【授業計画と授業の方法】
第1回 ガイダンス
「歴史人口学」とは何か? 第1回 日本の歴史における人口増加の四つの波 縄文時代の人口循環、弥生時代の農耕化、14世紀以降の市場経済化、19世紀以降の工業化 第2回 経済社会化と人口成長 −江戸時代を中心に− 豊臣秀吉による戸口調査、江戸時代の宗門人別改帳、全国的人口調査 第3回 人口成長のメカニズム 17世紀〜 婚姻革命(「皆婚社会」の成立)、小農民の自立、生産革命と死亡率改善 第4回 人口の停滞へ 18世紀〜 人口減少の要因、気候の寒冷化による飢饉と疫病、大都市と人口減少 第5回 江戸時代の結婚 有配偶率、労働と結婚年齢、結婚の持続期間 第6回 江戸時代の出産 出生児数の決定要因、年齢別出生率、産み初めと産み終わり 第7回 江戸時代の人口調整① 出生率の低い都市部、都市・農村間の人口還流 都市経済の発展と人口 第8回 江戸時代の人口調整② 堕胎・間引き、出生制限の意味、堕胎・間引きの禁止へ 第9回 これまでの復習、中間試験 第10回 江戸時代の寿命 死亡要因(疾病、飢饉、凶作)、平均寿命、子どもの生存権 第11回 19世紀の工業化と人口成長 18世紀末〜19世紀の経済成長と人口回復、西欧医学の流入、死亡率の改善 第12回 戦後の人口循環 戦後の人口循環、人口の都市集中、国民皆保険制度と寿命 第13回 現代日本の家族とライフサイクルー江戸時代との比較から− 子供の養育期間、家族間の人間関係、高齢者の問題 第14回 現在の世界人口 地球人口の増加、先進諸国における出生率の低下、途上国の人口増加 第15回 現代日本の少子化と高齢化—まとめにかえて− 限られた資源と「豊かさ」を考える、少子化高齢化に適合した新たな社会システムの構築 (講義の方法) 講義は、15回すべてプリントを配布します。講義の前にプリントを用意しておきますので、それを取ってください。講義では、必要事項を板書しますので、配布プリントにそれぞれまとめて記入してください。板書を写真撮影することは禁止します。また、補助資料として、パワーポイントに画像を提示して説明を行います。15回の講義のうち、10回以上は課題を出し、それに対して回答してもらいます。課題に対する回答は、ポータルサイトの「課題提出欄」に直接入力をお願いします。回答のフィードバックは、次回講義時のはじめに行います。 テキスト・参考書
(参考書)鬼頭宏『人口から読む日本の歴史』(講談社学術文庫、2000年、2022年)
授業時間外の学修
(事前学修)
前回のプリント(必要事項を記入し、各自で作成したもの)をよく読んで、次回の講義に参加するようにしてください。歴史的展開を重視する講義ですので、必ず読んでおいてください。 (事後学修) 講義終了後に、その回に学んだことに関する課題を提出することがあります。15回の講義のうち、10回以上は課題を出しますので、それに対して回答することによって復習するようにしてください。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
課題の提出(20%) 中間試験(30%) 期末試験(50%) (成績評価の基準) 到達目標1:縄文時代から現代までの日本の人口動態の歴史的変遷を理解できていること。 到達目標2:江戸時代の人口増加、停滞、減少の要因について理解できていること。 到達目標3:現在の少子高齢化が歴史的なシステムの転換点であることを理解できていること。 備 考
1.毎回配布資料とパワーポイントを使用し、全回「講義」形式で進める。
2.講義プリントをよく読み、予習・復習(各回予習・復習とも30分程度)を行うこと。 3.板書や画面内容の写真撮影は禁止しています。必ず自筆すること。 担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

