シラバス情報
|
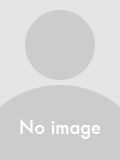
教員名 : 小畑 拓也
|
授業科目名
文芸創作特論
開講年次
1年
開講年度学期
2024年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
担当教員名
小畑 拓也
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
日常の言語活動の延長線上に位置しながら、より多層的で複雑な情報伝達を実践・実現する文芸創作という行為を、作者・発信者と読者・受信者のギャップを埋める「翻訳/翻案」の要素を軸に捉え直し、読解・表現の精度を高めることを目指す。 (受講生の到達目標) 到達目標1:それぞれの言語・文化的特性から生じるギャップを埋めるための英語-日本語間の翻訳の文章をまとめることができる。 到達目標2:メディアの違いがもたらす翻案の特性と制約を分析的に把握し、批評的文章にまとめることができる。 到達目標3:多様なメディアを併用して行われる表現の中で文章表現が担う役割を認識した上で、その特性を捉えた表現技法を駆使した文章をまとめることができる。 【授業の概要】
英語-日本語間の翻訳やメディア横断的な翻案の事例を元に、言語の文法構造や文化的な差異、メディア特性の違いが生む表現の多様性を確認し、文体模倣の実践を通じて精確な表現技法の習得を目指す。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 講義:オリエンテーション 第2回 講義・演習:翻訳の分析と実践 小説1 第3回 講義・演習:翻訳の分析と実践 小説2 第4回 講義・演習:翻訳の分析と実践 小説3 第5回 講義・演習:翻訳の分析と実践 戯曲1 第6回 講義・演習:翻訳の分析と実践 戯曲2 第7回 講義・演習:翻訳の分析と実践 戯曲3 第8回 講義・演習:翻訳の分析と実践 映画・ドラマ字幕1 第9回 講義・演習:翻訳の分析と実践 映画・ドラマ字幕2 第10回 講義・演習:翻訳の分析と実践 映画・ドラマ字幕3 第11回 講義:翻案の分析 小説の映像化1 第12回 講義:翻案の分析 小説の映像化2 第13回 講義:翻案の分析 ノベライゼーション1 第14回 講義:翻案の分析 ノベライゼーション2 第15回 講義・演習:翻案の分析と実践 メディアミックスの諸相 (授業の方法) 第2回〜第10回は英語圏の小説・戯曲・映画・ドラマが日本語に翻訳される際の言語文化的な位相差に注目して分析を進め、「翻訳文体」らしい表現と日本語的な表現の両極/折衷的な文章を構成するための技法を確認・訓練する。 第11回〜第14回は小説が映画化・ドラマ化される事例、映画・ドラマが小説化される事例の分析を通して、メディア表現ごとの特性と制約について批評的文章をまとめる。 第15回はメディアミックスという環境下で文章表現が担う役割を分析し、その特性を捉えた表現技法を駆使した文章をまとめる。 テキスト・参考書
(テキスト)資料を配信する。
(参考書)授業中に紹介する。 授業時間外の学修
(事前学修)
2回目の授業以降、前回の授業で提示されたキーワードの辞書・事典・関連書籍等による定義・解説を整理しておくこと。 (事後学修) 授業内容を整理・応用して、創作・批評の実践を進めること。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
授業への取り組み(50%)、毎回提出の課題(50%) (成績評価の基準) 到達目標1:英語から日本語への翻訳の文章を日本語として読みやすい形でまとめることができる。 到達目標2:翻案事例の分析を的確な批評的文章にまとめることができる。 到達目標3:多様なメディア間の橋渡しとなる言語表現の技法を駆使した文章をまとめることができる。 備 考
翻訳の課題として文芸分野の英語資料を用いるため、大学教養レベルの英語読解力が必須となるので、相応の覚悟をもって臨まれたい。
課題提示と提出および授業時間外の質疑応答はMicrosoft Teams上で行うので、PC等のデバイス・ネットワーク環境を整えておくこと(オンライン授業に切り替えられた場合には、Teamsの会議機能を利用してリアルタイムで授業を進行する)。 担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

