シラバス情報
|
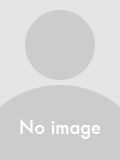
教員名 : 木下 祐輔
|
授業科目名
社会保障特論
開講年次
1年
開講年度学期
2024年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
担当教員名
木下 祐輔
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
【授業の目的】
日本の社会保障制度の内容や役割・課題について,実生活との関係を通じて理解する 【到達目標】 1.医療や介護,年金,生活保護といった,社会保障制度・政策に関する基礎的な知識を習得する 2.将来生じうる生活上のリスクに対する対処方法について,自分の頭で考えて論じることができる 【授業の概要】
社会保障を考える上で重要な基礎的な考え方と,政治や経済との関係というマクロの視点とともに,個人の生活や自己決定,キャリアプランやライフコースにも大きな影響を与えるものというミクロの視点の両面から,日本の社会保障について学ぶ。
特に,わが国の社会保障給付の多くは「申請主義」をとっている。 制度の現状や問題点に関する理解を深めるだけでなく,「制度を活用する」という観点で,実際のケース事例を紹介しながら社会保障のあり方を考察する。 また,授業全体を通じて,将来自分が困難な状況に陥った場合の対処方法について考えられる内容としたい。 【授業計画と授業の方法】
【授業計画】
1.イントロダクション—社会保障の見取り図[教科書:序章] 2.社会保険と民間保険—社会保障の考え方を知る[教科書:第7章] 3.社会保障の歴史と構造[教科書:第8章1〜3項] 4.社会保障と財政問題[教科書:第8章4項] 5.病気になったら(1)—医療保険制度の仕組み[教科書:第1章] 6.病気になったら(2)—現状と課題[教科書:第1章] 7.要介護になったら(1)—介護保険制度の仕組み[教科書:第3章] 8.要介護になったら(2)—現状と課題[教科書:第3章] 9.老後の生活はどうなる(1)—年金制度の仕組み[教科書:第4章] 10.老後の生活はどうなる(2)—現状と課題[教科書:第4章] 11.生活の糧を失ったら—生活保護制度の仕組み[教科書:第2章] 12.仕事を失ったら—雇用保険制度の仕組み[教科書:第5章] 13.子ども・子育て支援[教科書:第2章2項] 14.社会保障の課題と今後の展望[教科書:第8章5項] 15.全体総括 【授業の方法】 担当教員による講義形式で行う。特に社会保障の柱となる医療・介護・年金については,2回に分けて前半を考え方や制度の解説を中心に行い,後半をケース事例を紹介することによる実践的な内容とする予定である。 授業では配布するレジュメを基に解説を行うが,理解を助けるために,授業中に内容に関する新聞記事や動画(ニュース)を見ていただく場合がある。 テキスト・参考書
椋野美智子・田中耕太郎 ,「はじめての社会保障〔第20版〕:福祉を学ぶ人へ」,有斐閣アルマ,2023年,ISBN:978-4-641-22215-1(※必ず最新版を入手すること)
授業時間外の学修
事前学習として教科書を読み,予告されたテーマについて,新聞や雑誌,インターネットなどを通じて社会保障に関する記事やニュースに目を通しておいてほしい。
また,授業終了後は,配布したレジュメや教科書の内容を復習しておいてほしい。 成績評価の方法と基準
【小テスト(40%:10%×4回)+最終レポート(60%)=100%】
4日間の集中講義のなかで,最後に時間を取って理解度を確認するための小テストを行う。 また,最終レポートでは,これまで授業で学んだ視点や考え方を踏まえて考察されているかどうかを確認する。 備 考
この授業での学びが「転ばぬ先の杖」や「転んでも立ち上がれる杖」として,未来を生きる皆さんの助けになればと思う。
最後に,授業中の私語など,他の受講生の迷惑になる行為には厳しく対処する。 担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

