シラバス情報
|
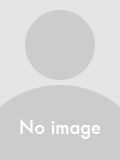
教員名 : 宗像 智仁
|
授業科目名
原価計算論
開講年次
2年
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-MN-204L
担当教員名
宗像 智仁
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・商業の関係科目 この授業の基礎となる科目
工業簿記・会計学概論・経営戦略論
次に履修が望まれる科目
管理会計論
【授業の目的と到達目標】
授業の目的:様々な原価計算の方法を用いて計算できることに加え、その方法の背後にあるロジックを説明できるようになることを目的とする。
受講生の到達目標: 1. 様々な原価計算の手続きや計算方法が説明できるようになる。 2. 原価計算の方法の背後にあるロジックを説明できるようになる。 【授業の概要】
原価計算システムは企業にとって不可欠な測定のシステムである。企業は原価計算システムを通じて製造プロセスで付加された価値を測定することにより、利益計算や活動の管理、そして価格決定をはじめとするさまざまな意思決定を行うことができる。
この科目は工業簿記の知識を前提としながら、原価計算基準を踏まえてさまざまな原価計算の方法について学習する。 【授業計画と授業の方法】
1. 原価計算の目的「講義」
講義全体の説明を行い、原価計算の目的について学習する。 2. 原価の概念「講義」 様々な原価の概念について学習する。 3. 原価の費目別計算「講義」 材料費、労務費、経費という原価の費目別分類の処理について学習する。 4. 原価の部門別計算「講義」 部門別に原価を集計する際の処理について学習する。 5. 個別原価計算「講義」 個別原価計算の方法について学習する。 6.単純総合原価計算・減損・仕損の処理「講義」 単純総合原価計算と減損・仕損の処理について学習する。 7. 工程別総合原価計算「講義」 工程別総合原価計算について学習する。 8.組別総合原価計算「講義」 組別総合原価計算について学習する。 9. 等級別総合原価計算・連産品の総合原価計算 等級別総合原価計算と連産品の総合原価計算について学習する。 10. 標準原価計算・差異分析「講義」 標準原価計算と差異分析について学習する。 11. 直接原価計算「講義」 直接原価計算の方法について学習する。 12. ABC・ABM「講義」 伝統的な原価計算の批判とそれに対するABCの方法について学習する。 13. 原価企画「講義」 原価企画の考え方について学習する。 14. 品質原価計算「講義」 品質原価計算の考え方について学習する。 15. ふりかえり「講義」 これまでの講義の総括を行う。 15回すべてでスライドを投影して講義を行う。 適宜、板書も行う。 テキスト・参考書
教科書の指定はない。
スライドを用いて講義を行う。 参考書は以下の通りである。 高橋賢(2015)『テキスト原価会計』(第2版)中央経済社。 廣本敏郎・挽文子(2015)『原価計算論』(第3版)中央経済社。 授業時間外の学修
スライドと各自がとったノートを読み返し、講義内容について復習する。
成績評価の方法と基準
平時の課題や小テスト(30%)と期末試験(70%)で評価する。
基準は到達目標に則る。 備 考
工業簿記の知識をある程度持っているという前提で講義を進める。
進捗や理解度に応じて講義内容を変更する可能性がある。 担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

