シラバス情報
|
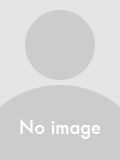
教員名 : 神﨑 稔章
|
授業科目名
金融論2
開講年次
2年
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-208L
担当教員名
神﨑 稔章
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・商業の関係科目 この授業の基礎となる科目
金融論1
次に履修が望まれる科目
貨幣経済学
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
本講義の目的は、基礎編としての金融論1を踏まえて、金融をより深く理解する上で必要な経済ファイナンスや制度の知識を学ぶことにある。金融論2では、経済主体の金融行動や金融機関の機能、金融市場等の定義や専門用語を説明できることを目的とする。また、情報の非対称性やデリバティブや金利と資産価格、ポートフォリオ、企業金融、金融規制等の金融理論を図示化し、計算できることも目的とする。以上の観点から、受講生が金融現象やそのエッセンスに関心を持ちつつ、金融の考え方を体系的に把握できるようになることを目指す。 (受講生の到達目標) 到達目標1:金融の考え方や専門用語の知識を問う問題に正しく答えることが出来る。 到達目標2:金融市場のデータの読み方や傾向を説明できる。 到達目標3:逆選択、モラルハザード、株式と債券の収益プロフィール、信用創造や貨幣乗数、オプション、スワップ、単利と複利、現在価 値と将来価値、利回りと債券価格、割引配当モデル、ポートフォリオ、モジリアーニミラー理論を中心とする概念を図の作成 や計算から説明することができる。 【授業の概要】
(授業の目的)
本講義の目的は、金融を理解する上で必要な基礎的な経済知識を学ぶことにある。金融論1に引き続き、金融論2では、現代社会の動向を踏まえた金融の制度的側面や理論的側面を、経済主体の金融行動や金融機関の機能、金融市場、及び金融規制の役割から学ぶと同時に、金融市場のデータを用いて規模や動向も学ぶ。加えて、情報の非対称性や流動性の供給、利回りと資産価格の関係性や、ポートフォリオ、デリバティブ、利回り曲線を用いた金融経済による理論を学ぶことで、銀行や企業や家計等の経済主体の行動を論理的に整理する力を養う。金融現象を捉えるため必要な数式は、連立方程式の他、高校数学程度の知識が必要になる。統計に関しては、平均や分散や共分散の理解が必要になる。 【授業計画と授業の方法】
第1回 オリエンテーション
金融論2の講義の進め方・金融的流通・産業的流通・金融取引の経済的意義(講義) 第2回 我が国の金融システムとその特徴(1)(講義) 金融システムの機能・貯蓄投資差と資金過不足・資金循環勘定 第3回 我が国の金融システムとその特徴(2)(講義) 分業主義・専門銀行主義・メインバンク制・金融の国際化・金融ビッグバン 第4回 金融仲介機関の役割と流動性の供給(1)(講義) 間接金融と直接金融及びリスク負担・資産変換機能・逆選択・モラルハザード・情報生産機能 第5回 金融仲介機関の役割と流動性の供給(2)(講義) ハイパワードマネー・信用創造・貨幣乗数・本源的預金 第6回 地域を巡る資金の流れ(講義) 域際収支と国際収支・移輸出と移輸入・その他経常移転 第7回 金融市場(講義) 短期金融市場・長期金融市場・収益プロフィール 第8回 デリバティブ取引の意義と役割(JPXによる外部講師による講義) 我が国の証券取引所の市場区分の再編(プライム・スタンダード・グロース)・JPX市場における投資家層、 企業のデリバティブ利用事例・ナイトセッション 第9回 デリバティブ理論と市場(1)(講義) 米市場と先物取引・日経平均と先物取引・先渡と先物・限月 第10回 デリバティブ理論と市場(2)(講義) オプション・スワップ・二項モデル・BSモデル 第11回 利子率(講義) 単利と複利・現在価値と将来価値・安全資産と危険資産・リスクプレミアム・フィッシャー仮説 第12回 債券利回りと資産価格(講義) 利付債券と割引債券・債券価格と裁定・イールドカーブ・効率性市場仮説とバブル 第13回 家計の金融行動(講義) 金融資産選択行動(資産選択理論) 第14回 企業の金融行動(講義) 企業の実物投資行動・資本市場の不完全性とモジリアーニミラー理論 第15回 金融規制(講義) 信用秩序の維持・自己資本規制・預金保険制度を中心とするプルーデンス政策 (授業の方法) 授業は15回全て、パワーポイント等で作成されたスライドを用いて教員が講義する形で行う。必要に応じて、定義や計算問題の解説等は、黒板に記載する。講義資料は事前にTeams等で配布する。講義内中に復習問題を出す。 テキスト・参考書
(テキスト)
事前に講義資料を配布する。 (参考書) 家森信善『ベーシック+】金融論 』中央経済社、2016年。 吉野直行『改訂版 社会と銀行』放送大学教育振興会、2014年。 授業時間外の学修
(事前学修)
事前に配布する講義資料を用いて、予習を行うこと。また、必要に応じて参考書を参考にしてください。 (事後学修) 講義時間中に出題する練習問題に取り組んでください。また、次回講義時の解説により、練習問題の回答が間違っていた場合や理解が足りないと感じた場合は、復習してください。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
期末試験(100%) (成績の基準) 到達目標1: 金融の考え方や専門用語の知識を問う問題に正しく答えることが出来ている。 到達目標2: 金融データに関する知識を問う問題に正しく答えることが出来ている。 到達目標3: 逆選択、モラルハザード、株式と債券の違い、信用創造や貨幣乗数、オプション、スワップ、単利と複利、現在価値と将来価値、利回りと債券価格、割引配当モデル、リスクの平均と分散、モジリアーニミラー理論、イールドカーブを中心とする概念について、図表を用いて表現できたり計算問題を解くことができる。 備 考
我が国の最新の証券取引所の最新動向を金融証券業界の外部講師(JPX:日本取引所)からお話し頂く予定ですが、講義回の内容に若干の変更が生じる場合があります。
担当教員の実務経験の有無
無
実務経験の具体的内容
|

