シラバス情報
|
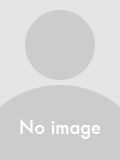
教員名 : 森本 幾子
|
授業科目名
地域経済史
開講年次
3年
開講年度学期
2024年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-303L
担当教員名
森本 幾子
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
経済史,日本経済史
次に履修が望まれる科目
日本経済論
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
この講義では、日本経済発展の基盤となった近世・近代の地域経済の歴史について学びます。とくに、受講生が大学生活を送る尾道を中心とした瀬戸内地域の歴史的風土や経済的特質をふまえ、それがどのような変遷を経て現在の地域産業に結び付いているかということを中心に学びます。その上で、今後の地域経済の在り方について、自分なりの意見を持つことが本講義の目標です。 (到達目標) 到達目標1:北前船と尾道商人間における商取引の特徴について説明できるようになること。 到達目標2:瀬戸内地域の遊女と地域経済の関係について説明できるようになること。 到達目標3:宮島、金刀比羅宮など瀬戸内地域の寺社の役割と観光地化の変遷について説明できるようになること。 【授業の概要】
現在、地方の政治・経済を見直すことへの関心が高まってることをふまえ、本講義では主に、近世期(江戸時代)・近代(とくに明治時代)の瀬戸内地域を対象とした地域経済の歴史について学びます。とくに、瀬戸内地域と他地域との商品取引から経済的特質を、経済的発展にともなって公認された遊廓の存在から女性たちの労働形態と地域経済の関係を、さらに海運業の発達にともなう海上安全祈願の広まりから金刀比羅宮や宮島などの観光地化について学ぶなかで、当時の瀬戸内地域経済の特徴と現在の地域経済の課題を関連付けて理解できるようになります。
【授業計画と授業の方法】
第1回 ガイダンス
近世・近代における瀬戸内地域の景観と経済活動の特徴について 第2回 第1章 瀬戸内地域経済の発展と北前船Ⅰ 日本の北方地域と瀬戸内経済の関係、肥料取引にみるアイヌ社会と瀬戸内経済 第3回 第2章 瀬戸内地域経済と北前船Ⅱ 仕切状からみた北前船商人と尾道商人の取引の特徴①商取引における仕切状の役割 第4回 第3章 瀬戸内地域経済と北前船Ⅲ 仕切状からみた北前船商人と尾道商人の取引の特徴②地域間価格差による利潤獲得 第5回 第4章 瀬戸内地域経済と北前船Ⅳ 北陸地域への瀬戸内産品移出と「尾道ブランド」の創出 第6回 第5章 商取引における「為替金」の役割 尾道商人による他国商人への為替金貸与と金融的優位性の確保 第7回 第6章 遠隔地間取引に関するまとめ 遠隔地間取引の特徴、中間試験 第8回 第7章 瀬戸内地域の遊女と地域経済Ⅰ 御手洗における遊女の営業形態と地域経済 第9回 第8章 瀬戸内地域の遊女と地域経済Ⅱ 遊女たちの労働環境・労働条件、人身売買と地域経済 第10回 第9章 海上安全祈願から観光業へⅠ 商品流通網の発展と海難事故、瀬戸内地域における金刀比羅宮の役割 第11回 第10章 海上安全祈願から観光業へⅡ 宮島の経済的特質、観光地としての宮島の役割 第12回 第11章 尾道の地域活性化と来訪者の力 全国からの行商人の来訪と地域経済の関係、社会的分業の細分化 第13回 第12章 自然災害の歴史と地域の課題 失われゆく「民俗知」、歴史的地名の重要性、災害を後世に伝える方法 第14回 第13章 造船関連企業と瀬戸内経済 造船関連企業が瀬戸内経済に与えた影響 第15回 第14章 地域経済史を学ぶ意義と現在の課題との関係 地域産業、地域経済活性化、観光業からみる歴史的特徴と課題 講義は、15回すべてプリントを配布します。講義の前にプリントを用意しておきますので、それを取ってください。講義では、必要事項を板書しますので、配布プリントにそれぞれまとめて記入してください。板書を写真撮影することは禁止します。また、補助資料として、パワーポイントに画像を提示して説明を行います。必要に応じて、課題を提出してもらうことがあります。課題に対する回答は、ポータルサイトの「課題提出欄」に直接入力をお願いします。回答のフィードバックは、次回講義時のはじめに行います。 テキスト・参考書
必要に応じて講義プリントを配る。
授業時間外の学修
講義中に適宜紹介する。
成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
課題提出(20%) 中間試験(30%) 期末試験(50%) (成績評価の基準) 到達目標1:近世・近代の遠隔地間商取引(地域間価格差による利潤獲得など)について正しく答えることができる。 到達目標2:女性の労働環境と地域経済の関係について正しく答えることができる。 到達目標3:寺社への信仰の広まりと観光地化との関係について正しく答えることができる。 備 考
1.毎回配布資料とパワーポイントを使用し、全回「講義」形式で進める。
2.講義プリントをよく読み、予習・復習(各回予習・復習とも30分程度)を行うこと。 3.板書や画面内容の写真撮影は禁止しています。必ず自筆すること。 担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

