シラバス情報
|
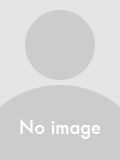
教員名 : 井本 伸
|
授業科目名
経済学入門2(マクロ)
開講年次
1年
開講年度学期
2024年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-102L
担当教員名
井本 伸
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための必修科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・商業の関係科目 この授業の基礎となる科目
経済学入門1(ミクロ)
次に履修が望まれる科目
マクロ経済学1
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
この授業の目的は、これから経済学を学ぶために必要なマクロ経済学の基礎を学ぶことです。経済理論は大きく分けて、ミクロ経済学とマクロ経済学に分けられます。前期で学んだ「経済学入門1(ミクロ)」とあわせて、経済理論全体の基礎的な考え方を身に付けてもらうことになります。 (受講生の到達目標) 到達目標1; マクロ経済学で扱うデータや専門用語ついて説明できる。 到達目標2; GDPについて説明できる。 到達目標3; IS-LMモデルの基本を説明できる。 【授業の概要】
マクロ経済学を学ぶために必要な専門用語およびデータについて学びます。
特に、マクロ経済学は国全体の経済を扱うため、国全体の豊かさを測る指標であるGDPについて詳しく学びます。例えば、GDPとは何か、どのように計算するのか、どのような構成要素を持つのか、などです。 最終的には、IS-LMモデルと呼ばれる理論を学びます。この理論を修得することにより、GDPがどのようにして決まるのか、なぜ景気が悪くなるのか、政府はどのような経済政策を行えばいいのか、などを理解できるようになります。 経済理論は数式を用いて経済現象を記述するため、簡単な式の計算だけでなく、連立方程式なども解ける必要があります。 【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 1章:マクロ経済学で学ぶこと マクロ経済学への期待・マクロ経済学とミクロ経済学・マクロ経済問題・マクロ経済変数と私たちの暮らし 第2回 2章:マクロ経済学と日本経済 経済を見る上で重要なマクロ変数(経済成長率・失業率・物価・株価・国際収支・外国為替レート) 第3回 3章(前半):GDP(国内総生産) GDPの概念(GDPの定義・付加価値・国内生産の意味)・GDPと所得 第4回 3章(後半):GDP(国内総生産) 名目GDPと実質GDP・GDP統計の実際・GDPの三面等価・GDPギャップ 第5回 4章:消費と貯蓄 消費関数・日本の消費関数・消費と貯蓄 第6回 5章:企業の投資 投資の概念・投資の決定要因・日本の投資関数 第7回 6章:政府の支出 政府財政の状況・財政の役割・財政支出と景気の関係の実際・財政赤字の意味 第8回 7章(前半):総需要の経済学 総需要の分析・ケインズ経済学・総需要の決定-・過少雇用均衡の可能性と完全雇用の達成 第9回 7章(後半):総需要の経済学 乗数理論・経済構造と政策効果・貯蓄のパラドックス・モデルの限界 第10回 8章(前半):金融市場の分析 貨幣の役割・貨幣の定義・貨幣創造 第11回 8章(後半):金融市場の分析 貨幣需要の理論・現実の貨幣供給と金利の関係・マクロ金融政策の政策手段・日本の貨幣乗数 第12回 9章(前半):IS-LMモデル 財市場と金融市場の相互関係・財市場の均衡 —IS曲線の導出—・IS曲線の性質 第13回 9章(後半):IS-LMモデル 貨幣市場の均衡 —LM曲線の導出—・LM曲線の性質・IS-LMモデルの完成 第14回 10章(前半):IS-LMモデルを使った分析 労働市場の不均衡・財政・金融政策の効果・経済構造と経済政策の効果 第15回 10章(後半):IS-LMモデルを使った分析 数式を使った整理・計算問題 (授業の方法) 授業は15回全て、パワーポイント等で作成されたスライドを用いて教員が講義する形で行います。必要に応じて、計算問題の解説などは、黒板に書く場合もあります。講義資料は事前にkyouzaiフォルダなどで配布しますので、テキストと合わせて事前学修に役立ててください。毎回講義内容に関連した練習問題を出題します。講義終了後、当日中にポータルを利用して解答を送ってください。練習問題の解説や質問のフィードバックは次回講義時に行います。 第9回講義の終了後、7章までの範囲について中間テストを行います。出題は講義終了後にポータルを通じて行いますので、毎回の練習問題と同様にポータルを通じて回答を行ってください(中間テストは講義時間中に行うわけではありません)。 テキスト・参考書
家森信善「ベーシック+ マクロ経済学の基礎」中央経済社、2021年
授業時間外の学修
(事前学修)テキストの該当箇所および事前配布している講義資料を読むことにより予習を行ってください。
(事後学修)講義時間中に出題する練習問題に取り組んでください。また、次回講義時の解説により、練習問題の回答が間違っていた場合や理解が足りないと感じた場合は、復習してください。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
毎回の練習問題(30%) 中間テスト(10%) 期末テスト(60%) (成績評価の基準) 到達目標1;マクロ経済学の用語に関する知識を問う問題について正しく答えることが出来ている。 到達目標2;GDPに関する知識を問う問題について正しく答えることが出来ており、またGDPに関する計算問題が解けている。 到達目標3;IS-LMモデルに関する知識を問う問題について正しく答えることが出来ており、またIS-LMモデルの計算問題が解けている。 備 考
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

