シラバス情報
|
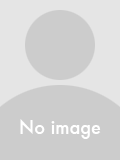
教員名 : 灰谷 謙二
|
授業科目名
日本語学特講
開講年次
1年
開講年度学期
2023年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
灰谷 謙二
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
方言文法と日本語史の関係をとおして、日本語の時空間的変異を総合的に把握する視点を学ぶ。 (受講生の到達目標) (知識・技能) 到達目標1:方言文法と日本語史に関する基礎的文献によって、日本語文法の成立と展開に関する知識を習得する。 (思考力・判断力・表現力) 到達目標2:コーパスや実地調査をもとに収集したデータを用いて、方言文法の分布と展開を日本語史と関連付けて考えることができ、それを発表レポートの形で説明できる。 【授業の概要】
小林隆2005『方言学的日本語史の方法』ひつじ書房、工藤真由美1995『アスペクト・テンス体系とテクスト−現代日本語の時間の表現−』ひつじ書房、佐々木冠渋谷勝巳工藤真由美井上優日高水穂2006『シリーズ方言学2方言の文法』岩波書店等を基礎文献として、『方言文法全国地図』と方言コーパス(COJADS)をもちいながら、受講生の出身方言における方言文法の史的展開を理解します。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 講義:ガイダンス 第2回 講義:『方言学的日本語史の方法』小林隆の方言文法史研究① 第3回 講義:『方言学的日本語史の方法』小林隆の方言文法史研究② 第4回 講義:工藤真由美氏のアスペクト研究① 第5回 講義:工藤真由美氏のアスペクト研究② 第6回 講義・演習:方言文法全国地図を読む 第7回 講義・演習:方言文法全国地図を読む② 第8回 講義・演習:方言文法全国地図を読む③ 第9回 講義・演習:方言談話資料・方言コーパスによる検証① 第10回 講義・演習:方言談話資料・方言コーパスによる検証① 第11回 講義・演習;日本語歴史コーパスによる検証① 第12回 講義・演習:日本語歴史コーパスによる検証② 第13回 講義 報告・発表 第14回 講義 報告・発表② 第15回 まとめ (授業の方法) 2−5回は指定論文の精読演習です。6回-12回は演習作業と報告をもとにディスカッションを行います。 13・14回は各自のたてたテーマに基づいた発表報告をおこないます。 テキスト・参考書
小林隆2005『方言学的日本語史の方法』ひつじ書房、
工藤真由美1995『アスペクト・テンス体系とテクスト−現代日本語の時間の表現−』ひつじ書房、 佐々木冠渋谷勝巳工藤真由美井上優日高水穂2006『シリーズ方言学2方言の文法』岩波書店等 国立国語研究所『方言文法全国地図』方言コーパス(COJADS) 授業時間外の学修
(事前学習)
指定論文通読、談話資料等からの関係資料検索などの作業 (事後学習) 授業時の討議で私的のあった疑問・要討議内容について作業をすすめ次回報告にそなえる。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
演習的作業の発表内容(50%)期末レポート(50%) (成績評価の基準) 到達目標1:方言文法と日本語史に関する基礎的文献によって、日本語文法の成立と展開に関する知識を習得できている。 (思考力・判断力・表現力) 到達目標2:コーパスや文献資料をもとに収集したデータを用いて、方言文法の分布と展開を日本語史と関連付けて考えることができ、それを発表しレポートの形で説明できている。 備 考
特殊講義ですが、少人数であることを考え、講義的な内容と演習作業的な内容を随時並行的におこないます。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

