シラバス情報
|
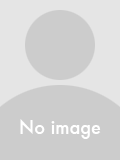
教員名 : 有吉 勇介
|
授業科目名
情報システム設計特論
開講年次
1年
開講年度学期
2023年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
有吉 勇介
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
情報技術特論
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目標)
情報システムの分析設計プロセスを理解し説明できるようになる。ソフトウェアの設計図であるUML図の作成と説明ができるようになる。 (受講生の到達目標) 1:情報システムの分析設計プロセスについて、説明ができるようになる。 2:UMLの各図について、説明ができるようになる。 3:UMLの各図について、作成できるようになる。 4:情報システムの分析設計プロセスを理解し、それに沿って仕様書作成ができるようになる。 【授業の概要】
文献講読に実習を交えて情報システムの分析設計プロセスについて理解することを目指します。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回ユースケース分析:ユースケース図(輪講、演習) 第2回ユースケース定義:イベントフローとシナリオ(輪講、演習) 第3回ユースケースの流れ:アクテイビティ図(輪講、演習) 第4回画面設計:画面イメージ、画面遷移図(輪講、演習) 第5回 ドメイン分析:オブジェクト指向と概念クラス図(輪講、演習) 第6回ロバストネス分析:BCEモデルとロバストネス図(輪講、演習) 第7回相互作用分析:シーケンス図とコミュニケーション図(輪講、演習) 第8回アーキテクチャ設計:VOPCと統合クラス図、ライフサイクル分析図(輪講、演習) 第9回クラス設計、属性設計:設計クラス図Ver.1(輪講、演習) 第10回相互作用設計: 設計シーケンス図、設計コミュニケーション図、設計クラス図Ver.2(輪講、演習) 第11回SysML1 :要求図(輪講、演習) 第12回SysML2:ブロック定義図、内部ブロック図、パラメトリック図 (輪講、演習) 第13回 設計仕様書作成1 :クラス設計(演習) 第14回 設計仕様書作成2 : 属性設計(演習) 第15回 設計仕様書作成3 : 相互作用設計(演習) (授業の方法) 基本的には、各回の授業は、文献輪講のあと、演習課題に取り組みます。 テキスト・参考書
(テキスト)
井上樹著『ダイアクラム別UML徹底活用第2版』翔泳社 授業時間外の学修
(事前学修)
発表者はテキストの担当個所をまとめて資料スライドを作成しておいてください。出てくるプログラム等は必ず動かして確認しておいてください。分からないことがあったり、問題が発生した場合は、演習が始まる前までに学生同士で話し合ったり、教員に質問したりしてくださ い。発表者以外はテキストをあらかじめ読んで内容を把握しておいてください。分からないことがあれば、演習中に解決するようにしてください。 (事後学修) 演習中に動作確認できなかったプログラム等は、次回までに動作確認しておいてください。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
担当個所の口頭発表(50%) 授業中の発言等、演習への参加態度(50%) (成績評価の基準) 1:情報システムの分析設計プロセスについて、説明ができる。 2:UMLの各図について、説明ができる。 3:UMLの各図について、作成できる。 4:情報システムの分析設計プロセスを理解し、それに沿って仕様書作成ができる。 備 考
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

