シラバス情報
|
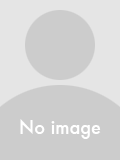
教員名 : 津村 怜花
|
授業科目名
簿記論特論
開講年次
1年
開講年度学期
2023年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
津村 怜花
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
会計学概論、簿記入門、商業簿記
次に履修が望まれる科目
財務会計特論
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
会計を考えるうえで、会計基準などを支える土台としての知識である複式簿記を学ぶことは有益である。このため、本講義では、複式簿記の生成から会計学への発展過程を学ぶ。 (受講生の到達目標) 到達目標1.複式簿記の起源説と要件について説明できる。 到達目標2.複式簿記から簿記理論、そして会計理論への生成過程について説明できる。 【授業の概要】
日本では、2010年より国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards:IFRS)が導入され、会計基準の変更等も行われている。このような中、会計基準などを考えるうえで土台となる知識として複式簿記を学ぶことは重要である。本講義では、13〜14世紀に複式簿記が生成した過程にさかのぼり、複式簿記の根本原理を学ぶとともに、その後会計学へと複式簿記が理論的に発展する過程の理解を深めることを目的としている。このために、講義中に多々質問するので、ただ説明を聞くのではなく、自分の考えを発言するなど、積極的に講義に参加するよう努める必要がある。
【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 オリエンテーションー債権債務の記録ー 第2回 複式簿記の誕生と起源説(序章) 第3回 フランスの簿記事情と会計規定の成立・展開(第1章) 第4回 ネーデルラント会計史の現代的意義(第3章) 第5回 15〜19世紀のイギリスの簿記事情(第4章) 第6回 アメリカへの複式簿記の移入と簿記理論の体系化(第5章) 第7回 株式会社会計の起源(第7章) 第8回 株式会社制度確立期の財務報告実務(第8章) 第9回 株式会社と会計専門職業(第10章) 第10回 会計理論の生成と展開1(第13章) 第11回 会計理論の生成と展開2(第13章) 第12回 和式帳合と複式簿記の輸入(第6章) 第13回 日本における複式簿記の理論展開(配布資料) 第14回 現代会計へのプロローグ(結章) 第15回 これまでの内容の確認と質疑応答 (授業方法) 最初に本日の講義内容を教員が説明する。その後、各自の作成したミニレポートを報告するとともに、討論を行うことで、理解を深めていく。 テキスト・参考書
(テキスト)
野常男・清水泰洋編著『近代会計史入門』同文舘出版、2019年。 各自、購入すること。 この他、必要な資料は別途配布する。 (参考書) 三光寺由実子『中世フランス会計史ー13-14世紀会計帳簿の実証的研究ー』同文舘出版、2011年。 中野常男『会計理論生成史』中央経済社、1992年。 中野常男編著『複式簿記の構造と機能—過去・現代・未来—』同文館出版、2007年。 平林喜博編著『近代会計成立史』同文舘出版、2005年。 ジェイコブ・ソール著・村井章子訳『帳簿の世界史』文藝春秋、2015年。 授業時間外の学修
(事前学修)
テキストの該当箇所をよく読み、各自で予習を行う。担当となっている者は、テキストの該当箇所についてミニレポートを作成し、報告に備える必要がある。 (事後学修) 理解が足りないと思う内容については、該当するテキストや講義資料、参考文献を読み直すなどして、理解を深めること。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
報告(60%) 質疑(40%) (成績評価の基準) 到達目標1.複式簿記の起源説と要件について、報告や討論に際して適切に説明できている。 到達目標2.複式簿記から簿記理論、そして会計理論への生成過程について、関連する授業回における報告や討論に際して適切に説明できている。 備 考
授業内容について、講義の進行速度、受講生の理解度に合わせて若干の変更もあり得る。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

