シラバス情報
|
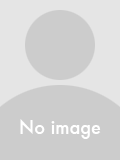
教員名 : 西村 剛
|
授業科目名
経営学特論
開講年次
1年
開講年度学期
2023年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
担当教員名
西村 剛
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
経営学総論、経営戦略論、経営管理論、経営組織論
次に履修が望まれる科目
経営組織論特論
【授業の目的と到達目標】
「経営学の方法と歴史」について講義する。経営学という学問の本質を探り、社会科学という分野における経営学の存在意義や存在根拠を究明していく。経営学は実践的学問と言われることもあるが、本特論では、既述のような究明により、経営学を現象面から考察するだけでなく、方法論的視点から検討することができるようになる。
【授業の概要】
日本の経営学の成立には、増地庸治郎がかつて「骨をドイツから取り、肉をアメリカに求めて、その地盤のうえに漸次研究を重ねてきたのが、今日の我が経営経済学である」と言うように、ドイツ経営経済学とアメリカ経営管理学(論)の影響を受けてきたことが明らかである。そのため本特論では、先ずそうしたドイツやアメリカにおいて展開された経営学の理論の足跡を辿る。また同時に日本へそうした理論を研究し、日本独自の経営学を成立させようとした我が国経営学者の理論を検討する。
【授業計画と授業の方法】
授業計画
経営学の本質に迫るため「方法的に接近すること」、「歴史的に接近すること」の両側面から検討を行う。前者は経営学で議論されてきた方法問題を検討することである。後者は経営学の生成からの発展過程を歴史的に考察することである。経営学の本質究明のためには、その両者の相互補完的究明が必要である。「方法的接近」とは経営学方法論であり、「歴史的接近」とは経営学史に他ならない。それらの方法を用いながら日本やドイツの斯学の先学者たちの足跡を辿り、経営学の本質、存在意義、存在根拠などを明らかにしていきたい。 (1)経営学の方法論の意義と論点 ①経営学方法論とは (2)経営学の方法論の意義と論点 ②方法論を学ぶ意義 (3)経営学の方法論の意義と論点 ③経営学方法論の論点について (4)経営学の研究対象 ①経営学の研究対象は「企業」か (5)経営学の研究対象 ②経営学の研究対象は「経営」か (6)経営学の国籍と名称 ①ドイツと経営経済学 (7)経営学の国籍と名称 ②アメリカと経営管理論 (8)経営学の国籍と名称 ③日本と批判経営学 (9)経営学史の意義と位置づけ ①経営学史の意義 (10)経営学史の意義と位置づけ ②経営学史の位置づけ (11)経営学史の対象と方法 ①経営学史の対象とは (12)経営学史の対象と方法 ②経営学史の方法について (13)日本経営学の生成と展開 (14)経営学の開拓者たち ①経営学部の成立 (15)経営学の開拓者たち ②神戸大学経営学部の軌跡 授業の方法 講義形式と参加型形式の両方の形式により進めていく。講義形式とは板書、その他PowerPointなども適宜使用しながら、必要に応じて関係資料を配付ものであるが、他方で参加型形式をとるので受講生による講義内容に関する報告を求めることもある。 テキスト・参考書
田中照純『経営学の方法と歴史』ミネルヴァ書房 1998年
上林憲雄・清水泰洋・平野恭平編著『経営学の開拓者たち ー神戸大学経営学部の軌跡と挑戦ー』中央経済社 2021年 渡辺敏雄『現代経営経済学の生成 方法論的展開』文眞堂 2022年 西村剛『経営組織論序説』晃洋書房 2003年 古林喜樂『経営経済学』千倉書房 1980年 古林喜樂『経営学方法論序説』三和書房 1967年 経営学史学会監修 上林憲雄編著『人間と経営』文眞堂 2021年 経営学史学会監修 田中照純編著『ニックリッシュ』文眞堂 2012年 経営学史学会監修 片岡信之編著『日本の経営学説2』文眞堂 2013年 上記以外については、その都度指示する。 授業時間外の学修
事後学修:講義した内容についてノートを熟読し、さらに講義内で紹介した文献などで知識を深めて欲しい。
成績評価の方法と基準
講義に臨む姿勢、レポート等によって総合的に評価する。
備 考
ドイツ語文献を使用することがあります。
担当教員の実務経験の有無
無
実務経験の具体的内容
|

