シラバス情報
|
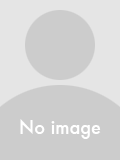
教員名 : 津村 怜花
|
授業科目名
財務会計特論
開講年次
1年
開講年度学期
2023年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
担当教員名
津村 怜花
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
会計学概論、財務会計論、簿記論特論
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
本講義では、企業会計原則や企業会計基準などを踏まえ、必要な会計処理のみならずなぜそれら原則・基準が設定されたのかを考察することを目的とする。 (受講生の到達目標) 到達目標1.各回で取り扱うテーマにおいて、どのような会計処理を行う必要があるか説明できる。 到達目標2.なぜそのような会計処理を行う必要があるのか、また当該会計処理に問題がないかなど、他の基準等との整合性を踏まえ説明することができる。 【授業の概要】
会計学には、大きく分けて外部の利害関係者に経営活動の成果を伝達する財務会計と、組織内部の利害関係者に経営管理に関する情報を提供する管理会計とに二分される。
その中で財務会計は、外部の利害関係者に対する報告に着目する学問領域であることから、順守すべき社会的ルールとしての企業会計原則や企業会計基準等を熟知することが求められる。さらに、会計の国際化が進み国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)とのコンバージェンスが進む今日においては、これらのルールを熟知するのみならず、財務報告を行う上で適切な会計処理とは何かを考える力も求められている。以上のことから、高度な会計処理が可能であることのみならず、その処理をなぜ行わなければならないのか、企業会計原則をはじめとしたルール、また収益認識会計基準のように新たに公開された会計基準などについて、それらのルールを知るだけではなく、設定された背景をも知る必要がある。 このため、本講義では、収益認識に関する会計基準などのカレントトピックスなどを取り上げ、これらを企業会計原則や企業会計基準、そして国際財務報告基準から改めて求められる会計処理を考察することとする。これにより、会計処理を行う理由を含め、理解することを目的とする。 【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
第1回 オリエンテーション 第2回 財務会計の機能と制度(第1章) 第3回 利益測定と資産評価の基礎概念(第2章) 第4回 会計理論と会計基準(第3章) 第5回 財務諸表の作成と公開(第12章) 第6回 連結財務諸表の公表制度(第13章) 第7回 財務諸表の活用①(配布資料) 第8回 財務諸表の活用②(配布資料) 第9回 課題報告① 第10回 課題報告② 第11回 会計の国際化の潮流(配布資料) 第12回 収益認識に関する会計基準(第6章) 第13回 論文レビュー① 第14回 論文レビュー② 第15回 論文レビュー③ (授業方法) 第1回目の授業時に、各受講生の報告担当箇所を定める。担当となった授業回については、該当するテキストの章をまとめたレポートを報告してもらう。その内容を踏まえて、教員が授業内容の解説など、補足説明を行うとともに、他の受講生からの質問を踏まえ、授業内容を深めるための討論を行う。 テキスト・参考書
(テキスト)
桜井久勝著『財務会計講義』中央経済社。(その折の最新版) (参考書) 桜井久勝『財務諸表分析』中央経済社。 中央経済社編集『新版 会計法規集』中央経済社。 辻山栄子編著『IFRSの会計思考 過去・現在そして未来への展望』中央経済社。 この他、必要に応じて文献を紹介する。 授業時間外の学修
(事前学修)
授業に向けた予習として、必ずテキストの外と箇所を読むこと。報告担当者については、テキスト内容をレポートとしてまとめてくる必要がある。 (事後学修) 授業内に十分理解できていないと思う箇所については、復習として授業資料や該当するテキストの章の読み直し等を行い、知識を深めること。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
報告(60%) 質疑など、授業への参加態度(40%) (成績評価の基準) 到達目標1.担当した報告内容において、どのような会計処理を行う必要があるか説明できている。 到達目標2.会計処理の仕方について、他の基準等との整合性を踏まえた質問や説明ができている。 備 考
受講生の理解度に応じて、授業内容について若干の変更もありうる。
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

