シラバス情報
|
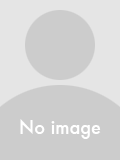
教員名 : 森本 幾子
|
授業科目名
経済史
開講年次
2年
開講年度学期
2023年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-212L
担当教員名
森本 幾子
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 商業) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・商業の関係科目 この授業の基礎となる科目
日本歴史の流れ、日本経済論
次に履修が望まれる科目
日本経済史、地域経済史
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
本講義の目的は、日本の政治経済が、近代以降、どのような国内的・国際的環境のもとで変遷してきたのかを学ぶことです。とくに、日本が初めて本格的に世界市場と競争し、対外戦争に至るまでの過程や条件について学び、それが日本の産業革命とどのような結びつきを持っているのかを学習することによって、現在日本が抱える課題について自分なりの意見を持つことが本講義の最終目的となります。 (受講生の到達目標) 到達目標1:開国後の日本経済の状況について説明できるようになること。 到達目標2:日本の産業革命の特徴について説明できるようになること。 到達目標3:日清・日露戦争の原因、結果、国内市場や国際市場への影響を説明できるようになること。 【授業の概要】
本講義では、開国以降の日本経済がどのような条件のもとに形成されてきたのかを日本の産業革命と日清・日露戦争を関連付けて学びます。日本の産業革命は、外国資本を排除したなかで企業勃興が進み、それに対する銀行の融資が行われたことに特徴があります。日本は、当時のグローバルスタンダードから外れた特殊な経済的条件の下で、近代的税制・銀行設立が進められ、やがて日清戦争・日露戦争の過程で企業勃興が展開することになりました。本講義ではとくに、日本が開国以降、なぜ、外国資本を排除しながら近代化が進められたのか、どのような輸出産業を軸として産業革命が起こったのか、日清・日露戦争の歴史的な意義は何であったのかをそれぞれ結び付けて学ぶことによって、日本の資本主義の特徴について理解できるようになります。
【授業計画と授業の方法】
第1回 ガイダンス
開港以降の日本経済を学ぶ意義、経済史の方法論 第2回 第1章 世界的大不況の中の日本経済 先進諸国の大不況とイギリスの役割、金本位制度、銀本位制度について 第3回 第2章 明治新政府による海外視察と民業育成 岩倉使節団の海外視察による近代化のグランドデザイン 第4回 第3章 西南戦争と国内のインフレ状況 地租改正と秩禄処分、征韓論と武士の世の終焉、戦争鎮圧に伴う国内金融市場の混乱 第5回 第4章 殖産資金と銀行の設立 外国資本排除の下での殖産興業、富岡製糸場にみるイギリス・フランス資本の排除 第6回 第5章 松方デフレ政策と日本銀行の設立過程 不換紙幣の整理と日本銀行の役割、徹底した緊縮財政政策 第7回 第6章 明治維新と北海道・沖縄 北海道と沖縄が日本の領土となった歴史的経緯について、北方地域と東アジアへの視点 第8回 第7章 日清戦争について学ぶ前に 中間試験 現在の中国経済と日本経済の関係、これまでの内容のまとめと中間試験 第9回 第8章 日清戦争開始への道 朝鮮半島をめぐる日清対立、日清戦争と広島、戦争を支えた経済力 第10回 第9章 日清戦後の企業勃興 下関講和条約の締結、金本位制への移行と産業の発展、製糸業、紡績業の発展 第11回 第10章 日露戦争について学ぶ前に 現在のロシア経済と日本経済の関係、日清戦争後の朝鮮半島の位置づけ、戦争と国内世論 第12回 第11章 日露戦争開始への道 外国債(ロンドン・ニューヨーク)と増税による戦費調達、近代的軍事技術と陸海工廠の役割 第13回 第12章 日露戦後処理と日本経済 ポーツマス条約の締結、南満州鉄道株式会社の経営、疲弊する農村 第14回 第13章 日露戦後の国内状況 紡績業を担った女工たち、労働運動と社会主義運動の激化、産業の発展と都市人口の増加 第15回 第14章 産業革命と日清・日露戦争の関係(総括) 日本人のアジア観、西洋人の日本人観の形成、文学作品・ルポタージュにみる明治の日本 (授業の方法) 講義は、15回すべてプリントを配布します。講義の前にプリントを用意しておきますので、それを取ってください。講義では、必要事項を板書しますので、配布プリントにそれぞれまとめて記入してください。板書を写真撮影することは禁止します。また、補助資料として、パワーポイントに画像を提示して説明を行います。15回の講義のうち、10回以上は課題を出し、それに対して回答してもらいます。課題に対する回答は、ポータルサイトの「課題提出欄」に直接入力をお願いします。回答のフィードバックは、次回講義時のはじめに行います。 テキスト・参考書
(参考書)石井寛治『日本の産業革命 日清・日露戦争から考える』(講談社学術文庫、2012年)
授業時間外の学修
(事前学修)
前回のプリント(必要事項を記入し、各自で作成したもの)をよく読んで、次回の講義に参加するようにしてください。歴史的展開を重視する講義ですので、必ず読んでおいてください。 (事後学修) 講義終了後に、その回に学んだことに関する課題を提出することがあります。15回の講義のうち、10回以上は課題を出しますので、それに対して回答することによって復習するようにしてください。 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
課題の提出(30%) 中間試験(20%) 期末試験(50%) (成績評価の基準) 到達目標1:開港後の日本経済の状況(税制、金融機関の整備、国際関係など)について正しく答えることができる。 到達目標2:日本の産業革命の特徴(製糸業・紡績業・その他在来産業・重工業の展開)について正しく答えることができる。 到達目標3:日清・日露戦争の原因、結果、その国内市場や国際市場への影響について正しく答えることができる。 備 考
1.毎回配布資料とパワーポイントを使用し、全回「講義」形式で進める。
2.講義プリントをよく読み、予習・復習(各回予習・復習とも30分程度)を行うこと。 3.板書や画面内容の写真撮影は禁止しています。必ず自筆すること。 担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

