シラバス情報
|
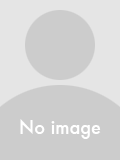
教員名 : 藤岡 秀英
|
授業科目名
社会政策
開講年次
3年
開講年度学期
2023年度前期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-EC-305L
担当教員名
藤岡 秀英
担当形態
単独
【科目の位置付け】
社会政策の背景・意義・課題について、人々の生活との関係をふまえて、歴史的に理解する科目です。
この授業の基礎となる科目
社会保障入門
次に履修が望まれる科目
社会保障
【授業の目的と到達目標】
(授業の目的)
経済社会の構造が大きく変化しています。社会政策は「社会問題」への政策的対応を明らかにする学問です。 この講義では、日本、世界の経済社会の質的・構造的変化を理解力を身に着けることを目的とします。 (受講生の到達目標) (1)少子化による人口減少問題を説明できる。 (2)経済格差をはじめとする「新しい社会問題」の原因を説明できる。 (3)経済社会問題の構造的原因と対策の有効性についての基本理論を説明できる。 【授業の概要】
(1)「市場の失敗」から社会保障の必要性、福祉国家の成熟と限界、「新しい社会問題」(格差問題)など幅広い社会問題への理解を深めます。
(2)年金、医療、介護などの社会保険、児童福祉、障がい者福祉、生活保護等の社会福祉を柱とする「社会保障制度」の基礎知識を学ぶこと。 (3)変化の激しい経済社会のなかで「生き抜く」ための視界を広げて、自由に生きるための自分自身の「ものの見方、考え方」の土台を作ること。 【授業計画と授業の方法】
(授業計画)
1日目 第1回 序章:学問としての社会政策 【ミクロ編:個人と社会】 第2回 「社会本質論」の系譜 社会名目論と社会実在論、現象学的社会学(蔵内数太) 第3回 政治倫理学と社会政策 J.ベンサム、J.S.ミルからJ.ロールズ、そして、M.サンデル 第4回 カトリック社会論と社会政策 2日目 【マクロ編:国家と集団】 第5回 社会政策の理論的展開 第6回 経済学と社会保障 第7回 社会保険の成⽴と社会保障への展開: ドイツとイギリス、アメリカの社会保障法 第8回 日本の社会保障制度 3日目 第9回 多元社会と福祉国家体制の成⽴ ネオ・コーポラティズムと「政府の失敗」 第10回 「新しい社会問題」 格差問題の原因と対策 第11回 格差問題の原因と対策 T.ピケティ『21世紀の資本』 4日目 【コミュニティ編】 第12回 平成の市町村合併と「地⽅創⽣総合戦略」 第13回 「コミュニティの失敗」 NPOはなぜ続かないのか 第14回 SNSは「新しいコミュニティ」を形成できるか? 第15回 生きものとして「人間の原点」に立ち返ること (授業の方法) 授業はパワーポイントのスライドを使って講義を行います。講義の途中で4回の小テストを実施します。 テキスト・参考書
足立正樹編著『現代の社会保障』(高菅出版,2023年)
授業時間外の学修
(事前学習)
参考書『現代の社会保障』を通読しておくことが望ましい。 (事後学習)令和元年から令和5年版『厚生労働白書』 ネット検索で本文を読むこと https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/index.html 成績評価の方法と基準
(成績評価の方法)
集中講義(4日間)を通じて小テストを実施します。 各回25点の配点により総合評価します。 (基準) 経済社会問題と社会政策のキーワードの意味を理解し説明できるかを問います。 備 考
担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

