シラバス情報
|
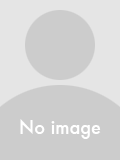
教員名 : 林 直樹
|
授業科目名
外国書講読2
開講年次
2年
開講年度学期
2023年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-CS-206L
担当教員名
林 直樹
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
【授業の目的】
(1)英語による専門的論説に触れることで英書に対する抵抗感を払拭し、類書を自ら読む姿勢を習慣づける。 (2)定評ある著者による最新の入門学術書を通じて、当該分野の研究が持つ現代的意義を理解する。 【受講生の到達目標】 (1)英文の論理(文章構成法)に習熟する。 (2)量よりも質、速さよりも深さを念頭に置き、文脈を精確に把握することができる。 【授業の概要】
テキストの著者は、チャールズ・バベッジによる階差機関の研究者として著名な人である。バベッジは、詩人バイロンの娘エイダ・ラヴレースのような良き理解者を得ながら、単なる計算機を超える「解析機関」を作ろうとした、社会思想史上においても非常に興味深い人物であると言える。
この講義ではしかし、特定の時代の特定の人物たちを掘り下げるのではなく、パスカルの計算機が登場した17世紀からスマホ全盛の21世紀までを視野に収め、通史的に「コンピューティングの歴史」を俯瞰する。教員はコンピュータの専門家ではないが、コンピュータへの関心を保ち続けたいアマチュアとして、そして同時に思想史研究者として、「革命」と評すしかないと著者が言う出来事が20世紀に生じ、いわゆる「コンピュータの時代」を創始した理由を受講生の皆さんとともに考えてみたいと思う。単純な進歩史観とは異なる視点が必ず現れてくるはずである。 【授業計画と授業の方法】
第 1回 Orientation 第 2回 History of Computing: the River Diagram【講義】 第 3回 Automatic Computation: Charles Babbage and Ada Lovelace (1)【講義】 第 4回 Automatic Computation: Charles Babbage and Ada Lovelace (2)【講義】 第 5回 Electronic Computing: Situating ENIAC, Framing EDSAC (1)【講義】 第 6回 Electronic Computing: Situating ENIAC, Framing EDSAC (2)【講義】 第 7回 The Computer Boom: IBM and the Seven Dwarves【講義】 第 8回 Overview of the Former Half and the Mid-term test【講義&課題】 第 9回 Revolution (1): Integrated Circuits【講義】 第10回 Revolution (2): Minicomputers【講義】 第11回 Revolution (3): The Microprocessor【講義】 第12回 Revolution (4): The Personal Computer【講義】 第13回 Revolution (5): Untold Histories【講義】 第14回 The Future of History: A New Master Narrative【講義】 第15回 Overview of the Latter Half and the Final test【講義&課題】 内容についてはテキストに準拠するが、毎回、教員が授業レジュメを作成して配布する。 中間テストまではコンピュータ時代の前史を扱う。知られざる歴史として非常に面白い。後半は現在のコンピュータ業界が形成されるまでの直接的経緯を詳細に取り上げるとともに、今後を展望する。締め括りは最終テストである。 テキスト・参考書
Doron Swade, "The History of Computing: A Very Short Introduction" (OUP, 2022)
授業時間外の学修
(事前学修)
レジュメの該当範囲にあらかじめ目を通しておくこと。 (事後学修) 単語の意味だけでなく英文の文脈を正しくつかみ取るために、よく復習すること。 成績評価の方法と基準
・中間試験50%、最終試験50%の合算で評価する。
・試験では、上述した到達目標に照らして満足のいく水準に到達しているかどうかを確認することに重きを置く。 備 考
Teamsで資料を共有しながら、対面で授業を進めていきます。通常の演習以上に少人数になるでしょうから、個別指導に近い環境でじっくり取り組みたい人にお薦めです。
担当教員の実務経験の有無
無
実務経験の具体的内容
|

