シラバス情報
|
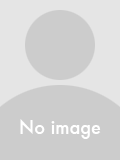
教員名 : 有馬 昌宏
|
授業科目名
経営情報論
開講年次
2年
開講年度学期
2023年度後期
単位数
2.00単位
科目ナンバリング
E-IN-201L
担当教員名
有馬 昌宏
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 情報) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・マルチメディア表現及び実習(実習を含む) この授業の基礎となる科目
経営シミュレーション
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
【講義の目的】
企業をはじめとする組織の経営においては、DX(デジタル・トランスフォーメーション)のなどのバズワードで謳われているように、情報通信技術(ICT)の活用は競争優位の獲得や組織の存続のためには必要不可欠であり、本講義では経営情報論の基礎理論から最先端のトピックスまでをカバーして、現代の組織の情報化実践に必要な知識を獲得し、ビッグデータからの情報の抽出や問題解決のためのスキルの向上を目指します。結果として、ITパスポートや基本情報技術者試験に出題される経営学や経営情報論や情報システム開発に関する問題が解答できるようになり、ICTを利活用する新しいビジネスの創出に向けてのヒントを獲得したり、社会に出てからのDXの取組に向けてのモチベーションを高めることが期待できます。 【受講生の到達目標】 1.データと情報と知識の違いが説明でき,それぞれが企業経営に果たす役割が説明できる。 2.Excelや統計解析専用ソフトウェア(SASなど)を利用して,データから情報を引き出せる。 3.決定木やアソシエーション分析などのデータマイニングの手法が適用できる。 4.情報システムの設計から運用までのプロセスがウォーターフォール型とアジャイル型の両方で説明できる。 5.情報セキュリティの必要性と確保の方法を説明できる。 6.ICTを活用したネットビジネスの特徴と可能性が説明できる。 【授業の概要】
ICT(情報通信技術)を企業や官公庁・自治体で使いこなして経営効果を高めるためには、技術だけではなく、人間や組織や社会の特性ならびにそれらの間の相互関係を理解し、その上で情報システムを開発・運用していく必要があります。本講義では、これらの広範にわたる理論や技術をカバーするために、気鋭の研究者による最新の教科書を使用し、経営情報論の基礎理論から最先端の議論までを解説します。また、データと情報と知識の違いを明確に認識した上で、Excelや無料で使用できるSAS OnDemand for Academicsなどのサービスを利用して、データから情報を引き出すための手法についても、実践を通じて習得を目指します。
【授業計画と授業の方法】
第1回 イントロダクション(講義の概要と講義の方法など)(講義、課題)
第2回 経営情報論の基礎(教科書第1章)(講義、課題、フィードバック) 第3回 経営情報論の基礎理論1(教科書第2章)(講義、課題、フィードバック) 第4回 経営情報論の基礎理論2(教科書第2章)(講義、課題、フィードバック) 第5回 経営情報システム観の変遷(教科書第3章)(講義、課題、フィードバック) 第6回 情報通信技術の進展と組織(教科書第4章)(講義、課題、フィードバック) 第7回 経営情報システムの設計・開発(教科書第5章)(講義、課題、フィードバック) 第8回 経営情報システムの管理(教科書第6章)(講義、課題、フィードバック) 第9回 情報通信技術を活用したビジネス・イノベーション(教科書第7章)(講義、課題、フィードバック) 第10回 ネットビジネス(教科書第8章)(講義、課題、フィードバック) 第11回 情報通信技術と組織コミュニケーション(教科書第9章)(講義、課題、フィードバック) 第12回 ビジネス・インテリジェンスとナレッジ・マネジメント(教科書第10章)(講義、課題、フィードバック) 第13回 情報通信技術と社会(教科書第11章)(講義、課題、フィードバック) 第14回 これからの経営情報論と情報化実践(教科書第12章)(講義、課題、フィードバック) 第15回 全体のまとめ(講義、フィードバック) 教科書に基づき、経営情報論の全体像が理解できるよう、パワーポイントのスライドや板書を活用して講義を行います。各回の講義の事前学習として、各回でカバーする教科書の指定箇所を一通り読んできてください(予習として30分、各回の講義のの宿題として、章の内容のまとめとキーワード抽出を課題として課します)。この際、理解できない箇所をノートに箇条書きにしておくなり、付箋(ポストイット)に書き込んで該当箇所に貼り付けておくとよいでしょう。講義後の事後学習として、改めて教科書の該当箇所を読み直し、毎回の講義で課す課題を行うことで復習をして、理解を完全なものとしてください(復習30分〜60分)。また、講義時間内では、データベース操作や簡単なデータマイニングについて、ExcelやSAS OnDemand for Academicsを利用しての実習も行う予定です。 テキスト・参考書
遠山曉・村田潔・古賀広志、「現代経営情報論」、有斐閣、2021年(ISBN:978-4-641-22178-9)
授業時間外の学修
必要に応じて、ポータルを通じて、あるいは講義時間中に指示します。一般的には,以下の内容で学修を行って下さい。
各回の講義の事前学習として、各回でカバーする教科書の指定箇所を一通り読んできてください(予習として30分、各回の講義のの宿題として、章の内容のまとめとキーワード抽出を課題として課します)。この際、理解できない箇所をノートに箇条書きにしておくなり、付箋(ポストイット)に書き込んで該当箇所に貼り付けておくとよいでしょう。講義後の事後学習として、改めて教科書の該当箇所を読み直し、毎回の講義で課す課題を行うことで復習をして、理解を完全なものとしてください(復習30分〜60分)。 成績評価の方法と基準
毎回の講義で課す教科書の内容を理解するための課題およびExcelやSASによるデータ解析やデータマイングに関する課題が1回で4%(講義時間内課題が1%,次週までの課題が3%)で15回の講義全体で60%、受講生の到達目標が達成できているかどうかを確認するための経営情報論に関するキーワードが適切に使用できるかどうかを問う穴埋め問題による定期試験が40%。
備 考
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

