シラバス情報
|
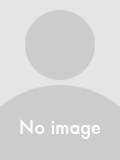
教員名 : 原 卓史
|
授業科目名
研究指導(論文指導)
開講年次
2年
開講年度学期
2022年度前期、2022年度後期
単位数
4単位
科目ナンバリング
担当教員名
原 卓史
担当形態
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
・卒業論文作成で学んだことを前提にして、課題設定・情報収集・論構成・執筆などについて、学生がより専門性の高い学術的意義のある修士論文にすることを目標とする。
【授業の概要】
・学生による演習発表を行う授業とする。
・授業の流れは以下の通りとする。①発表担当者を決める。②授業前日13時までに発表担当者は発表資料を作成し、チームズに資料をアップロードする。③その他の受講生と教員は、発表日までに発表担当者の発表資料に目を通しておく。④発表当日、教員・他の受講生を交えてディスカッションを行う。⑤回答できなかったことについて、次回の発表時に補足を行うとともに、さらに考察を深めた発表資料の作成を行う。 ・少人数で行う演習形式の授業となるため、原則として発表と質疑を前提とした双方向的な授業となる。教員が一方的に話をする授業は想定していない。 【授業計画と授業の方法】
第 1回 ガイダンス 授業の概要の説明(講義)
・事前課題 事前にガイダンス資料を読んでおく(60分) ・事後課題 授業の概要と方針を理解する(30分) 第 2回 研究計画①(講義) ・事前課題 事前に研究計画を立てる(120分) ・事後課題 研究計画の課題がどこか洗い出す(60分) 第 3回 研究計画②(講義) ・事前課題 研究計画の課題を修正する(120分) ・事後課題 さらに課題があれば研究課題を修正する(60分) 第 4回 先行研究①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第 5回 先行研究②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第 6回 先行研究③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第 7回 方法の吟味①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第 8回 方法の吟味②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第 9回 方法の吟味③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第10回 文献の渉猟・データ収集①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第11回 文献の渉猟・データ収集②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第12回 文献の渉猟・データ収集③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第13回 分析とアイディアの蓄積①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第14回 分析とアイディアの蓄積②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第15回 分析とアイディアの蓄積③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第16回 後期・初回ガイダンス(講義) ・事前課題 事前にガイダンス資料を読んでおく(60分) ・事後課題 授業の概要と方針を理解する(30分) 第17回 参考文献・引用箇所の情報化①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第18回 参考文献・引用箇所の情報化②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第19回 論文構成の再考①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第20回 論文構成の再考②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第21回 論文構成の再考③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第22回 図表の整え方①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第23回 図表の整え方②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第24回 図表の整え方③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第25回 文献リスト・注の整備①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第26回 文献リスト・注の整備②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第27回 文献リスト・注の整備③(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第28回 校正・印刷・提出①(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第29回 校正・印刷・提出②(演習) ・事前課題 発表担当者は発表資料(レジュメ)の作成を行い、他の受講生は作品を読む(120分) ・事後課題 発表担当者は質疑で出た課題を考え、他の受講生は作品を読み直す(60分) 第30回 口頭試問の準備(演習) ・事前課題 事前に修士論文の課題はどこかを自分なりに確認し、口頭試問の対策を行う(90分) ・事後課題 教員や他の受講生からもらった意見を踏まえ、さらに口頭試問の対策を行う(90分) 学生の論文執筆の進捗状況を考慮しながら、課題を設定する。 テキスト・参考書
学生が研究対象とする作家・作品。底本の指定を学生に行わせる。
授業時間外の学修
適宜紹介する。
成績評価の方法と基準
授業への取組50%、論文の完成度50%で評価する。
備 考
・対面・オンラインにかかわらず、teamsを使用する。
・オンライン授業は、teamsの「〇〇年度ゼミナール(原卓史)」チームの「大学院」チャネルを使用し、リアルタイムで授業を行う。授業用資料(レジュメ)、授業音声は、「大学院」チャネルの中のファイルにアップロードする。 ・発表資料の提出は、「〇〇年度ゼミナール」チームの「ファイル」の中に、学生発表資料用フォルダを作成し、その中に発表資料をアップロードする。 担当教員の実務経験の有無
実務経験の具体的内容
|

