シラバス情報
|
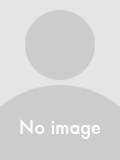
教員名 : 宋 娘沃
|
授業科目名
経営史
開講年次
2年
開講年度学期
2022年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-MN-213L
担当教員名
宋 娘沃
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
経営学入門
次に履修が望まれる科目
経営学総論、経営組織論、経営戦略論
【授業の目的と到達目標】
日本企業がどのようにして発展してきたのかが理解できる。
就職活動の際に、企業の選択する時、どの部分を重視するかが理解できる。 【授業の概要】
企業の経営活動はその企業を創業した経営者、社員から成り立っているが、その時期の経済発展や世界情勢、経営環境によって大きく変化する。この講義では、これまで日本経済を支えてきた商社、金融、産業に焦点をあてて学習する。具体的には戦後日本の商社、銀行システムの歴史的変遷からどのように発展してきたかを明らかにする。また、日本の産業の中でも自動車産業、半導体産業、電子産業の歴史的考察からその発展と衰退を明らかする。
【授業計画と授業の方法】
第1回 経営史とは何か(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)]
第2回 高度成長期の産業と企業(講義)「事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)」 第3回 企業間競争と産業の成長(講義)「事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)」 第4回 日本的生産システムの形成(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第5回 トヨタ生産システム(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第6回 日本企業のサプライヤー・システム(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第7回 大衆消費時代と電子産業の発展(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第8回 技術革新と大量生産(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第9回 技術経営の誕生(講義)[事前学習・事前課題ついて取り組む(所要時間は50分)] 第10回 技術導入と技術開発の組織能力(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第11回 財閥の多角化と組織(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第12回 三菱財閥の誕生と発展(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第13回 流通のイノベーション(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第14回 インターネット時代のマーケティング(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] 第15回 日本的経営とその変容(講義)[事前学習・事前課題について取り組む(所要時間は50分)] テキスト・参考書
授業時間外の学修
相田洋『電子立国日本の自叙伝』日本放送出版協会,1992年。
クレイトン・クリステンセン著 伊豆原弓訳『イノベーションのジレンマ 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社,2000年。 宮本又郎編『日本経営史』有斐閣,2010年。 宇田川勝『日本の自動車産業経営史』文眞堂,2013年。 宮本又郎・岡部桂史・平野恭平編著『1からの経営史』中央経済社,2014年。 成績評価の方法と基準
小テスト、定期試験、レポートなどを総合的に評価する。
備 考
講義の理解度を深めるため、参考文献を読むこと。オンラインで実施する場合、Zoomで行う。
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

