シラバス情報
|
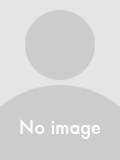
教員名 : 林 直樹
|
授業科目名
基礎演習1
開講年次
1年
開講年度学期
2022年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-CS-101S
担当教員名
林 直樹
担当形態
単独
【科目の位置付け】
この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
(1)テキストを読みこなし、内容を的確に要約できるようになるとともに、問題を自ら発見できるようになる。
(2)プレゼンテーションやディスカッションに必要な諸技能を習得する。 【授業の概要】
大学生は比較的、時間に余裕があるものだ。その余裕をアルバイトに費やすもよし、資格試験の勉強に費やすもよし、駄弁り(豊かな人間関係の構築に必須)に費やすもよし。はたまた明確なクラブ・サークル活動に勤しむもよし、あるいは当然のことながら、日々の授業課題に真摯に取り組むもよし。しかしそれでも、時間は余るであろう。留学を含めた旅をするもよし。ただしその旅の友として、本を一冊や二冊、電子書籍でも紙の書籍でも構わないが、持ち歩くことを薦めたい。必ずや内面世界が広がることだろう。言い換えれば、読書とは知的な旅を行うことに等しい。
世に読書の手引きは数多いが、この授業のテキストに指定した、小泉信三(かつての慶應義塾長)による『読書論』は特に名著とされ、半世紀以上にわたって読み継がれてきた。読書論の古典と呼んで差し支えないだろう。多少、言葉遣い等に抵抗を覚えるかもしれないけれども、慣れれば非常に読みやすく、また一文一文に読書家の知恵が詰まっている。本書をガイドとして、1年生の皆さんが知の世界への旅路についてくれるなら、教員としては非常に嬉しく思う。 【授業計画と授業の方法】
第 1回 ガイダンス(1)【演習】
第 2回 ガイダンス(2)【演習】 第 3回 第一章 何を読むべきか:古典について【演習&課題】 第 4回 第二章 如何に読むべきか【演習&課題】 第 5回 第三章 語学力について【演習&課題】 第 6回 第四章 翻訳について【演習&課題】 第 7回 第五章 書き入れ及び読書覚え書き【演習&課題】 第 8回 第六章 読書と観察【演習&課題】 第 9回 第七章 読書と思索【演習&課題】 第10回 第八章 文章論【演習&課題】 第11回 第九章 書斎及び蔵書【演習&課題】 第12回 第十章 読書の記憶(1)【演習&課題】 第13回 第十章 読書の記憶(2)【演習&課題】 第14回 第十章 読書の記憶(3)【演習&課題】 第15回 最終発表【演習&課題】 課題(個人発表およびグループ発表)の準備には数時間を要します。 テキスト・参考書
小泉信三『読書論』岩波新書(改版1964年)
授業時間外の学修
適宜、指示します。
成績評価の方法と基準
毎回の授業に対する準備、参加意欲、発言の積極性等を総合的に判断して評価します。
備 考
ディスカッションやプレゼンテーション(個人発表とグループ発表)の場では、単なる「レポート」(状況報告)にならないように、論点や疑問点を積極的に提示するよう心がけてください。なお、対面実施こそがふさわしい授業内容ですが、やむを得ない場合にはTeamsによるオンライン形式で実施します。その場合もなるべく対面の妙味を維持できるように努めますので、皆さんもご協力をお願いします。
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

