シラバス情報
|
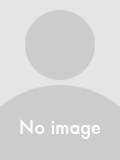
教員名 : 王 佳子
|
授業科目名
専門演習2b(卒業研究)
担当教員
王 佳子
開講年次
4年
単位数
2.00単位
学 期
2022年度後期
区分
週間授業
この授業の基礎となる科目
民法入門、民法、商法、企業法
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と概要】
この授業の目的は、株式会社が資金調達を行う際、道路貨物運送業・水運業を行う際や、友好的買収を行う際に生じうる法的問題を理解することにあります。
株式会社の経済活動は、数えきれないほどありますが、それを可能にしているのは潤沢な資金です。このことから、資金調達は、常に、株式会社の最重要な経済活動のひとつとして考えられます。資金調達については、ある者がほかの者から直接お金を借りるという直接金融と、ほかの者からお金を集めた者からお金を借りるという間接金融のふたつの形態が認識されており、前者が後者よりも効率的であると言われています。また、同じ直接金融でも、取引所を通した方が通さないよりも大規模な資金調達が可能になります。それでは、株式会社が取引所を通して資金調達をすることについてどのような規整が敷かれているでしょうか。この授業は、株式会社が自社の株式を上場させるために何をしなければならないか、上場を果たした後に、株式会社が自社の株式を購入していたり、購入することを検討していたりする者に対してどのような義務を尽くさなければならないか、そのような義務を履行させるためにどのような制度が設けられているかといった観点から、この問題を検討していきます。 また、資金調達がうまくいくと、株式会社は、幅広く活動を展開できるようになります。その際に、株式会社は、自社の活動内容に応じて、異なる規律を受けます。例えば、飲食業を営む株式会社は、食品衛生法やいわゆる食品リサイクル法といった法律を遵守しなければなりません。またホームセンターのような小売業者は、消費者契約法やいわゆる景品表示法関連のトラブルが生じないように事業を運営しています。この授業では、尾道市が海事都市と称されており、尾道市周辺では、道路貨物運送や水運を業とする株式会社が多いことを踏まえて、このような業種に属する株式会社がどのような法律の適用対象となり、どのような義務や責任を負うかを議論していきます。 さらに、具体的な業ではありませんが、株式会社がいわゆるM&Aを繰り返していくものですので、ここにも調達した資金が使われます。M&Aは、被買収会社の態度に応じて、敵対的買収と友好的買収に分かれ、日本では、後者の件数の方が圧倒的に多いです。株式会社が友好的買収を行う際に、買収会社の代表と被買収会社の代表が話合いを進め、合意に達すると、契約書を作成すると同時に、買収を行うことについてそれぞれの会社で承認を採ります。買収会社の代表が被買収会社の代表と話し合う事項として、買収を実現するために利用すべき制度や、買収の対価が挙げられます。同時に、友好的買収の交渉過程において、買収会社が被買収会社に対して自社の状況を明かすことが少なくないので、自社の状況に関する情報を悪用することを禁じる取決めが必要になりますし、相手方が買収を反故にすることを制限する取決めも必要になります。このような事項をどのようにすべきか、被買収会社が取決めに違反する場合にどのような措置を講じるべきかなどは、実務上の重要な課題となっています。また、話し合いの代表には取締役が務めるようになっていることから、友好的買収を行う株式会社の取締役が、自社の特徴や自社と被買収会社との関係性に照らして前述の事項を交渉したかどうか、既存株主や債権者の利益保護を図ったかどうかをめぐって争われることが頻繁に見られます。この授業では、このような問題を取り上げます。 【卒業研究について】
株式会社の経済活動に内在する法的問題について、卒業論文を作成していきます。
成績評価の基準等
授業への参加度50%、卒業論文50%
なお、卒業論文の審査は、論文の内容面と形式面から行う予定です。論文の内容面としては、問題点が提示されているかどうか、問題点に関する自分の意見が示されているかどうか、自分の意見を裏付ける素材が用いられたかどうかを基準として審査を行います。論文の形式面としては、文章作成の基本的な作法が守られているかどうか、誤字脱字があるかどうか、引用の体裁が適切であるかどうかを基準として審査を行います。 予習・復習へのアドバイス
指示した読み物には何度も目を通すことが重要です。
法学系の読み物は、すぐに頭に入ってこないことが多いですが、繰り返し読んでいくうちにすこしずつ理解できるようになります。 授業の中では、判例や論文を読むよう指示することがありますが、予習としても復習としても読んでみてください。 備 考
授業実施形態としては、大学の活動制限レベルによって変わることが予想されます。オンライン授業を実施する場合は、Teamsを利用します。
授業の実施形態にかかわらず、授業の中でディスカッションや研究指導を行います。 質問は、授業中でもTeams上のチャットでも受け付けますので、気軽にご連絡ください。 |

