シラバス情報
|
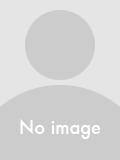
教員名 : 加藤 伸江
|
授業科目名
日本文学史2(中古)
開講年次
カリキュラムにより異なります。
開講年度学期
2020年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
J-JLT-212L
担当教員名
加藤 伸江
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(中学校・高等学校 国語) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・国文学(国文学史を含む。) この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
【授業の目的と到達目標】
中古文学作品の一端に触れ、成立背景やその後におよぼす影響について検討し、中古文学史の理解を深めます。
【授業の概要】
国風文化の時代、仮名で書かれた文学作品が多く誕生しました。その誕生には漢詩や和歌、歌物語など相互に影響を及ぼしたことが起因しています。多くの文学作品を誕生させるに至った中古文学史の流れを追い、その後の影響について考えます。
【授業計画と授業の方法】
第 1回 教養としての漢詩(白氏文集)
第 2回 勅撰集(古今集) 第 3回 和歌での交流(私家集、歌合) 第 4回 歌物語の登場(伊勢物語、大和物語) 第 5回 物語のはじめ(竹取物語、落窪物語) 第 6回 日記文学のおこり(土佐日記、蜻蛉日記) 第 7回 日記文学と儀式(紫式部日記) 第 8回 随筆の出現(枕草子) 第 9回 源氏物語の成立 第10回 源氏物語の発展 第11回 源氏物語の享受(更級日記) 第12回 源氏物語以後(堤中納言物語、浜松中納言物語) 第13回 歴史物語の意図(栄花物語、大鏡) 第14回 説話文学(今昔物語) 第15回 まとめ テキスト・参考書
プリントを配布します。
授業時間外の学修
授業時に適宜紹介します。
成績評価の方法と基準
レポート(65%)、出席・受講態度(35%)
備 考
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

