シラバス情報
|
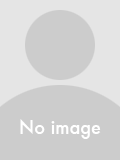
教員名 : 藤沢 毅
|
授業科目名
日本文学史4(近世)
開講年次
1年
開講年度学期
2019年度後期
単位数
2単位
科目ナンバリング
J-JLT-214L
担当教員名
藤沢 毅
担当形態
単独
【科目の位置付け】
教員の免許状取得のための選択科目
科目区分・・・教科及び教科の指導法に関する科目(中学校・高等学校 国語) 施行規則に定める科目区分又は事項等・・・国文学(国文学史を含む。) この授業の基礎となる科目
次に履修が望まれる科目
日本文学講読4(近世)
【授業の目的と到達目標】
近世文学の「流れ」を把握し、また個々の作品の「新しさ」を理解すること。具体的な例をもとに、自分の頭で考え、またまとめなおして他者に対して説明できるようになること。
【授業の概要】
近世文学史を概説する。近世は出版文化が起こり、栄えた時期であるため、常に出版という問題を意識しながら、諸ジャンルの作品を見ていく。文学史と言っても、作品名を暗記させるようなものにはしない。むしろ、作品一つ一つの「新しさ」を味わってもらえるようにしていきたい。同時に、大学で文学を学ぶ意味をも考えていく。
【授業計画と授業の方法】
第 1回 近世という時代…出版文化の成立
第 2回 仮名草子というジャンル…「ジャンルとは何か」をも考える。 第 3回 浮世草子というジャンル…近代以降の「主題」という捉え方では評価できない文学を知る。 第 4回 俳諧の成立…俳諧連歌から貞門、談林という流れを理解する。 第 5回 芭蕉の俳諧…芭蕉の俳諧理念を考える。 第 6回 蕪村と一茶、川柳…芭蕉以降の流れを追う。俳諧のまとめ。 第 7回 実録…本文の変遷を考える。テキストとは何か。 第 8回 読本…江戸時代の冒険ファンタジー? 第 9回 人情本…江戸時代の恋愛小説? 笑話本…「笑い」を生むための工夫とは? 第10回 草双紙(1)…赤本を素材に「絵を読む」。 第11回 草双紙(2)…黄表紙を素材にパロディという手法を考える。 第12回 役者似顔絵…歌舞伎と錦絵と草双紙の関係。 第13回 歌舞伎…歌舞伎とはどのような演劇か。 第14回 人形浄瑠璃…人形浄瑠璃とはどのような演劇か。 第15回 近世文学研究の魅力と課題 (受講者数、使用教室によって第12回〜14回の順が変動することがあります) テキスト・参考書
講義時に配布するプリント。
授業時間外の学修
適宜指示する。
成績評価の方法と基準
論述形式の試験(自筆ノートと配布プリントの持ち込みを可とする)(85%)。
講義中の発言、ミニレポートなどを加点する(15%)。 備 考
講義時には、板書されたことのみを写すのではないノート作りをし、それをもとに出力(他者に説明すること)できるよう復習してください。
担当教員の実務経験の有無
×
実務経験の具体的内容
|

